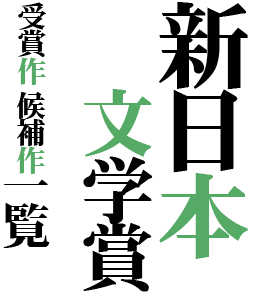新日本文学賞
第1回~第34回
昭和36年/1961年~
平成16年/2004年
1. 2. 3. 4. 5.平成16年/2004年
6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34.
| 主催 | 新日本文学会 |
| 対象 | 公募原稿(未発表原稿または締切以前1年未満に発行のサークル誌・同人誌に掲載したもの) |
|
第1回
|
昭和36年/1961年度=[ 締切 ] 昭和36年/1961年3月31日
=[ 決定 ] 昭和36年/1961年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和36年/1961年9月号【長編小説部門】【短編小説部門】選評掲載、10月号【評論部門】選評掲載
長編小説部門
短編小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第2回
|
昭和37年/1962年度=[ 締切 ] 昭和36年/1961年12月25日
=[ 決定 ] 昭和37年/1962年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和37年/1962年5月号選評掲載
長編小説部門
短編小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第3回
|
昭和38年/1963年度=[ 締切 ] 昭和37年/1962年12月20日
=[ 決定 ] 昭和38年/1963年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和38年/1963年5月号【短編小説部門】選考座談会掲載、6月号【長編小説部門】選考座談会【評論部門】選評掲載、11月号【長編小説部門】決定発表掲載
長編小説部門
短編小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第4回
|
昭和39年/1964年度=[ 締切 ] 昭和38年/1963年12月20日
=[ 決定 ] 昭和39年/1964年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和39年/1964年8月号【短編小説部門】【評論部門】選評掲載、9月号【長編小説部門】選評掲載
長編小説部門
短編小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第5回
|
昭和40年/1965年度=[ 締切 ] 昭和39年/1964年12月20日
=[ 決定 ] 昭和40年/1965年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和40年/1965年8月号【短編小説部門】選評掲載、9月号【長編小説部門】【評論部門】選評掲載
長編小説部門
短編小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第6回
|
昭和41年/1966年度=[ 締切 ] 昭和41年/1966年3月31日
=[ 決定 ] 昭和41年/1966年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和41年/1966年10月号選評(【小説部門】は座談会)掲載
小説部門
評論部門
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第7回
|
昭和42年/1967年度=[ 締切 ] 昭和42年/1967年4月30日
=[ 決定 ] 昭和42年/1967年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和42年/1967年10月号発表、11月号選評掲載
小説部門
評論部門
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第8回
|
昭和44年/1969年度=[ 締切 ] 昭和44年/1969年1月31日
=[ 決定 ] 昭和44年/1969年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和44年/1969年7月号選評掲載
小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第9回
|
昭和45年/1970年度=[ 締切 ] 昭和45年/1970年4月30日
=[ 決定 ] 昭和45年/1970年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和45年/1970年10月号選評掲載
小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第10回
|
昭和46年/1971年度=[ 締切 ] 昭和46年/1971年4月30日
=[ 決定 ] 昭和46年/1971年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和46年/1971年11月号選評掲載
小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第11回
|
昭和47年/1972年度=[ 締切 ] 昭和47年/1972年4月30日
=[ 決定 ] 昭和47年/1972年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和47年/1972年11月号選評掲載
小説部門
評論部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第12回
|
昭和48年/1973年度=[ 締切 ] 昭和48年/1973年4月30日
=[ 決定 ] 昭和48年/1973年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和48年/1973年12月号選評掲載
小説部門
評論部門
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第13回
|
昭和49年/1974年度=[ 締切 ] 昭和49年/1974年7月31日
=[ 決定 ] 昭和49年/1974年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和50年/1975年1月号選評掲載
小説部門
評論部門
ルポ部門
詩部門
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第14回
|
昭和50年/1975年度=[ 締切 ] 昭和50年/1975年7月31日
=[ 決定 ] 昭和50年/1975年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和51年/1976年1月号選評掲載
小説・戯曲部門
評論部門
ルポ部門
詩部門
|
|
|
第15回
|
昭和51年/1976年度=[ 締切 ] 昭和51年/1976年7月31日
=[ 決定 ] 昭和51年/1976年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和52年/1977年2月号選評掲載
小説・戯曲部門
評論部門
ルポ部門
詩部門
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第16回
|
昭和52年/1977年度=[ 締切 ] 昭和52年/1977年7月31日
=[ 決定 ] 昭和52年/1977年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和53年/1978年2月号選評掲載
小説・戯曲部門
評論部門
ルポ部門
詩部門
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第17回
|
昭和53年/1978年度=[ 締切 ] 昭和53年/1978年7月31日
=[ 決定 ] 昭和53年/1978年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和54年/1979年2月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第18回
|
昭和55年/1980年度=[ 締切 ] 昭和55年/1980年9月30日
=[ 決定 ] 昭和55年/1980年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和56年/1981年3月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第19回
|
昭和57年/1982年度=[ 締切 ] 昭和57年/1982年9月30日
=[ 決定 ] 昭和57年/1982年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和58年/1983年5月号選評掲載
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第20回
|
昭和59年/1984年度=[ 締切 ] 昭和59年/1984年9月30日
=[ 決定 ] 昭和59年/1984年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和60年/1985年8月号選評掲載
|
|
|
第21回
|
昭和63年/1988年度=[ 締切 ] 昭和63年/1988年9月30日
=[ 決定 ] 昭和63年/1988年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』昭和64年/1989年新年号[1月]選評掲載
|
|
|
第22回
|
平成2年/1990年度=[ 締切 ] 平成1年/1989年11月30日
=[ 決定 ] 平成2年/1990年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成2年/1990年夏号[7月]選評掲載
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第23回
|
平成4年/1992年度=[ 締切 ] 平成3年/1991年3月31日
=[ 決定 ] 平成4年/1992年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成4年/1992年冬号[1月]選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第24回
|
平成5年/1993年度=[ 決定 ] 平成5年/1993年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成5年/1993年夏号[7月]選評掲載
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第25回
|
平成6年/1994年度=[ 決定 ] 平成6年/1994年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成6年/1994年12月号選評掲載
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第26回
|
平成7年/1995年度=[ 締切 ] 平成7年/1995年8月31日
=[ 決定 ] 平成7年/1995年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成8年/1996年4月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第27回
|
平成8年/1996年度=[ 締切 ] 平成8年/1996年8月31日
=[ 決定 ] 平成8年/1996年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成9年/1997年4月号選評掲載
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第28回
|
平成9年/1997年度=[ 締切 ] 平成9年/1997年8月31日
=[ 決定 ] 平成9年/1997年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成10年/1998年4月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第29回
|
平成11年/1999年度=[ 締切 ] 平成10年/1998年8月31日
=[ 決定 ] 平成11年/1999年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成11年/1999年4月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第30回
|
平成12年/2000年度=[ 締切 ] 平成11年/1999年8月31日
=[ 決定 ] 平成12年/2000年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成12年/2000年5月号選評掲載
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第31回
|
平成13年/2001年度=[ 締切 ] 平成12年/2000年8月31日
=[ 決定 ] 平成13年/2001年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成13年/2001年5月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第32回
|
平成14年/2002年度=[ 締切 ] 平成13年/2001年8月31日
=[ 決定 ] 平成14年/2002年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成14年/2002年5月号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第33回
|
平成15年/2003年度=[ 締切 ] 平成14年/2002年8月31日
=[ 決定 ] 平成15年/2003年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成15年/2003年5・6月合併号選評掲載
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第34回
|
平成16年/2004年度=[ 決定 ] 平成16年/2004年
=[ 媒体 ] 『新日本文学』平成16年/2004年9・10月合併号選評掲載
|
|