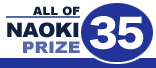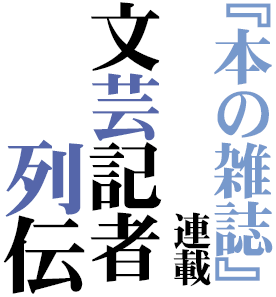新聞社に勤める文芸記者って、いったい何なのか。
直木賞とも縁が深いその存在を、歴史的に追ってみました。
直木賞とも縁が深いその存在を、歴史的に追ってみました。
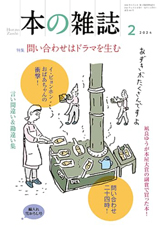
『本の雑誌』
令和6年/2024年2月号
(1月発売号)
令和6年/2024年2月号
(1月発売号)
第24回
いまの時代を生きる人たち
現役記者(各社)
―
―
『朝日新聞』中村真理子、『東京新聞』樋口薫など、現在文芸を担当する記者たち。
―
『本の雑誌』という月刊誌があります。そこで何か連載でも……というお話をもらってから早ン年。ようやくお互いのタイミングが合致して、令和4年/2022年3月号から頑張って始めることになりました。
テーマは、直木賞でも文学賞でもありません。「文芸記者」です。
直木賞に興味をもち出すと、この賞に関するアレやコレやが気になります。そのなかで、ずっと頭にあったのが文芸記者のことです。
作家や出版社、小説業界のことを日頃から取材し、その動向に寄り添いながら、新聞に直木賞のことをデカデカと取り上げては、多くの人たちにこの賞の存在を知らせてきた、アノ人たちです。
そもそも直木賞は、別にそこまで大きく扱うような賞じゃありません。なのに、他の賞に比べて報道陣の食いつき方が異常だ、とさんざん言われてきた歴史があります。さんざん言われてきたのに、何ひとつ是正する気配もなく、いまなお直木賞となれば無条件に派手な記事を仕立てるテイタラク。いったいあの人たちの頭の中身はどうなっているんだろう。ずっと疑問に思ってきました。
それで今回せっかくの機会なので、明治から現在まで日本の近現代文学をたどりながら、それぞれの時代の文学(というか文壇)に併走していた文芸記者について調べてみたい、と思ったわけです。
直木賞のハナシが中心じゃないんですけど、とりあえず、いまのところ連載は続けています。興味のありそうな文芸記者がいたら、ぜひ『本の雑誌』を覗いてみてやってください。 → 令和6年/2024年2月号の第24回で、どうにか無事に連載を終えました。直木賞とは関係ないことを調べて書くなんて、慣れないことをやりすぎて、疲れました。
[R6]2024/1/19
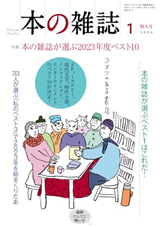
『本の雑誌』
令和6年/2024年1月号
(12月発売号)
令和6年/2024年1月号
(12月発売号)
第23回
面の皮が厚い人
鵜飼哲夫(読売新聞)
昭和34年/1959年
~
愛知県名古屋市生まれ。中央大学法学部卒。~
昭和58年/1983年、読売新聞社に入社。平成3年/1991年から文化部に所属し、積極的に現場を取材。直木賞・芥川賞の受賞者会見では変わった質問をすることでも知られ、名物記者として長年文壇を歩き回る。
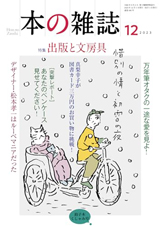
『本の雑誌』
令和5年/2023年12月号
(11月発売号)
令和5年/2023年12月号
(11月発売号)
第22回
生身の人間を大事にした人
小山鉄郎(共同通信)
昭和24年/1949年5月
~
群馬県伊勢崎市生まれ。一橋大学経済学部卒。~
昭和48年/1973年、共同通信社に入社。昭和59年/1984年に文化部に配属される。永井龍男をはじめとして数々の作家を取材。平成2年/1990年1月~平成6年/1994年5月には『文學界』でコラム「文学者追跡」を連載した。
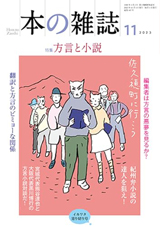
『本の雑誌』
令和5年/2023年11月号
(10月発売号)
令和5年/2023年11月号
(10月発売号)
第21回
断定を避けた人
由里幸子(朝日新聞)
昭和22年/1947年4月29日
~
京都府舞鶴市生まれ。大阪大学薬学部卒。~
昭和45年/1970年、朝日新聞社に入社。地方支局等を経て、学芸部に配属される。昭和55年/1980年頃から文芸担当となり、女性作家の活躍などを中心に多くの記事を書いた。年末の文芸年間回顧の記事は20年で計15回担当。
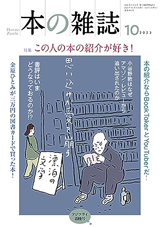
『本の雑誌』
令和5年/2023年10月号
(9月発売号)
令和5年/2023年10月号
(9月発売号)
第20回
郷土で生きると決めた人
久野啓介(熊本日日新聞)
昭和11年/1936年4月18日
~令和4年/2022年11月6日(享年86)
熊本県熊本市生まれ。熊本大学法文学部卒。~令和4年/2022年11月6日(享年86)
昭和35年/1960年、熊本日日新聞社に入社。東京支社を経て昭和41年/1966年、本社文化部に所属。石牟礼道子らと交流を結び、自らも雑誌編集や小説執筆を行う。社内ではぐんぐんと出世し、編集局長などを務めた。
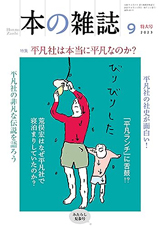
『本の雑誌』
令和5年/2023年9月号
(8月発売号)
令和5年/2023年9月号
(8月発売号)
第19回
長期連載で鍛えられた人
井尻千男(日本経済新聞)
昭和13年/1938年8月2日
~平成27年/2015年6月3日(享年77)
山梨県生まれ。立教大学文学部卒。~平成27年/2015年6月3日(享年77)
昭和37年/1962年、日本経済新聞社に入社。校閲部を経て昭和45年/1970年から文化部所属。文芸、出版を担当するかたわら、コラム「とじ糸」の執筆も任され、長く連載を担当した。平成9年/1997年退社。
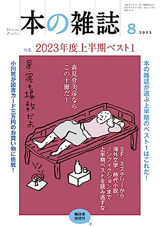
『本の雑誌』
令和5年/2023年8月号
(7月発売号)
令和5年/2023年8月号
(7月発売号)
第18回
出版ビジネスに精通した人
藤田昌司(時事通信)
昭和5年/1930年2月13日
~平成20年/2008年8月31日(享年78)
福島県生まれ。無線講習所修了。~平成20年/2008年8月31日(享年78)
昭和24年/1949年、時事通信社に入社。昭和40年/1965年に文化部記者となる。ベストセラーの舞台裏を取材し、文芸出版に関する分析記事を大量に書いた。昭和61年/1986年の定年後は嘱託として自ら図書編集に携わる。
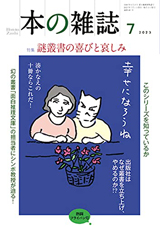
『本の雑誌』
令和5年/2023年7月号
(6月発売号)
令和5年/2023年7月号
(6月発売号)
第17回
エッセイでいじられる人
金田浩一呂(産経新聞、夕刊フジ)
昭和7年/1932年2月13日
~平成23年/2011年7月20日(享年79)
宮崎県生まれ。中央大学法学部卒。~平成23年/2011年7月20日(享年79)
昭和37年/1962年、産経新聞社に入社。整理部、甲府支社を経て教養部(のちの文化部)所属。昭和51年/1976年に『夕刊フジ』に異動。粗忽でトボけた言動を繰り返し、多くの物書きに愛された。
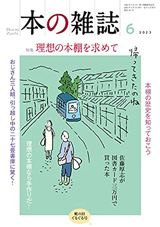
『本の雑誌』
令和5年/2023年6月号
(5月発売号)
令和5年/2023年6月号
(5月発売号)
第16回
多くの作家を怒らせた人
百目鬼恭三郎(朝日新聞)
大正15年/1926年2月8日
~平成3年/1991年3月31日(享年65)
北海道小樽市生まれ。東京大学文学部英文学科卒。~平成3年/1991年3月31日(享年65)
昭和27年/1952年、朝日新聞社に入社。学芸部、社会部、調査研究室を経て再び学芸部所属。文芸担当から編集委員となり、匿名批評の書き手として、攻撃的な毒舌ぶりで有名になった。昭和59年/1984年退社。
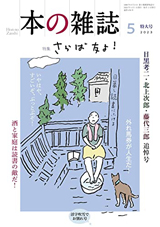
『本の雑誌』
令和5年/2023年5月号
(4月発売号)
令和5年/2023年5月号
(4月発売号)
第15回
文芸界の大事件で名を上げた人
伊達宗克(NHK)
昭和3年/1928年8月18日
~昭和63年/1988年1月15日(享年59)
愛媛県松山市生まれ。日本大学法学部新聞学科卒。~昭和63年/1988年1月15日(享年59)
昭和28年/1953年、東京日日新聞社に入社するが、翌年NHKに転職。報道局社会部記者として数々の事件を取材し、放送記者として活躍する。のちNHK解説委員、日大講師などを務めた。
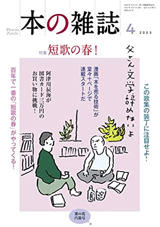
『本の雑誌』
令和5年/2023年4月号
(3月発売号)
令和5年/2023年4月号
(3月発売号)
第14回
書評欄を変えようとした人
杉山喬(朝日新聞)
大正7年/1918年5月2日
~没年不詳
埼玉県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。~没年不詳
昭和18年/1943年、朝日新聞社に入社。浦和支局時代に「本庄事件」に遭遇。その後、通信部を経て昭和27年/1952年に学芸部へ。昭和46年/1971年、読書欄担当として初めて編集委員となった。
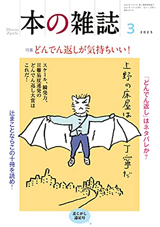
『本の雑誌』
令和5年/2023年3月号
(2月発売号)
令和5年/2023年3月号
(2月発売号)
第13回
恥かしそうに仕事した人
田口哲郎(共同通信)
昭和7年/1932年4月27日
~平成28年/2016年10月26日(享年84)
東京府北豊島郡生まれ。早稲田大学第二文学部卒。~平成28年/2016年10月26日(享年84)
昭和30年/1955年、共同通信社に入社。文化部に所属し、2年半の映画担当を経て文芸担当となる。昭和39年/1964年から約3年半、大阪支社に勤務。作家業のかたわら記者を続け、昭和50年/1975年に辞職。
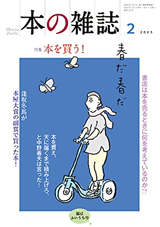
『本の雑誌』
令和5年/2023年2月号
(1月発売号)
令和5年/2023年2月号
(1月発売号)
第12回
自分で小説を書きたかった人
竹内良夫(読売新聞)
大正5年/1916年12月19日
~平成5年/1993年11月18日(享年77)
東京市生まれ。日本大学経済科卒。~平成5年/1993年11月18日(享年77)
海軍出征等を経て昭和21年/1946年、読売新聞社に入社。まもなく文化部所属となり、太宰治の心中事件を取材。記者のかたわらカストリ雑誌に多くの原稿を売り、また自ら同人雑誌にも参加した。出世には縁がなく、昭和46年/1971年に部長待遇で退職。

『本の雑誌』
令和5年/2023年1月号
(12月発売号)
令和5年/2023年1月号
(12月発売号)
第11回
文学の道をあきらめた人
森川勇作(北海道新聞)
大正7年/1918年1月4日
~平成20年/2008年8月21日(享年90)
北海道陸別村生まれ。弟子屈尋常高等小学校卒。~平成20年/2008年8月21日(享年90)
昭和9年/1934年、釧路新聞に勤めたのを皮切りに、旭川新聞、小樽新聞を経て、道内新聞の統合で昭和17年/1942年より北海道新聞記者。戦後、東京支社の社会部次長として山岡荘八「徳川家康」連載開始に携わった。
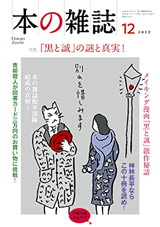
『本の雑誌』
令和4年/2022年12月号
(11月発売号)
令和4年/2022年12月号
(11月発売号)
第10回
騒がしい文化欄をつくった二人
平岩八郎、頼尊清隆(東京新聞)
(平岩)大正4年/1915年10月20日
~昭和63年/1988年5月21日(享年72)
(頼尊)大正4年/1915年5月14日
~平成6年/1994年9月2日(享年79)
(平岩)愛知県幸田町生まれ。法政大学社会学科卒。昭和15年/1940年、都新聞に入社。のち二度の離籍・復社を経る。~昭和63年/1988年5月21日(享年72)
(頼尊)大正4年/1915年5月14日
~平成6年/1994年9月2日(享年79)
(頼尊)大阪生まれ。東京帝国大学独文科卒。平岩と同期入社。20年以上平社員だったが、のち副部長、部長待遇。
両者ともに『東京新聞』文化部に長く務めた。
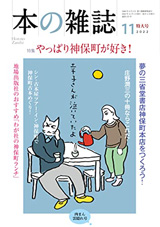
『本の雑誌』
令和4年/2022年11月号
(10月発売号)
令和4年/2022年11月号
(10月発売号)
第9回
クセのあるメンツに揉まれた人
高原四郎(東京日日新聞)
明治43年/1910年11月11日
~昭和62年/1987年4月9日(享年76)
東京市生まれ。東京帝国大学文学部卒。~昭和62年/1987年4月9日(享年76)
昭和8年/1933年、東京日日新聞社に入社。阿部眞之助率いる学芸部に所属し、文芸記者として活動。とくに菊池寛に可愛がられる。従軍記者等を務めたのち、戦後、学芸部に復帰。学芸部長、東京本社出版局長などを歴任。

『本の雑誌』
令和4年/2022年10月号
(9月発売号)
令和4年/2022年10月号
(9月発売号)
第8回
威光をバックに仕事した人
新延修三(東京朝日新聞)
明治38年/1905年2月26日
~昭和60年/1985年5月10日(享年80)
大阪市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。~昭和60年/1985年5月10日(享年80)
昭和3年/1928年、東京朝日新聞社に入社。学芸部に所属したのち、戦後は中京新聞出向を経て、『婦人朝日』『アサヒグラフ』の編集長を務める。昭和35年/1960年定年退職。「延岡修」名義の翻訳書もある。
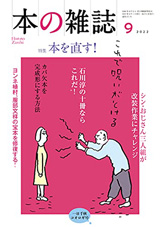
『本の雑誌』
令和4年/2022年9月号
(8月発売号)
令和4年/2022年9月号
(8月発売号)
第7回
最後まで取り乱さない人
渡辺均(大阪毎日新聞)
明治27年/1894年8月6日
~昭和26年/1951年3月16日(享年56)
兵庫県揖保川町生まれ。京都帝国大学文学部卒。~昭和26年/1951年3月16日(享年56)
大正8年/1919年、大阪毎日新聞社に入社。大正11年/1922年、学芸部記者として『サンデー毎日』創刊に参加。特別号「小説と講談」の編集等を担当。小説家、落語研究家としての顔も持つ。昭和26年/1951年、自殺。

『本の雑誌』
令和4年/2022年8月号
(7月発売号)
令和4年/2022年8月号
(7月発売号)
第6回
記者の仕事から離れて花ひらく
赤井清司(大阪朝日新聞)
明治22年/1889年
~没年不詳
大阪府四宮村生まれ。同志社大学英文科卒。~没年不詳
大正6年/1917年、大阪朝日新聞社に入社。大正11年/1922年、学芸部記者として『週刊朝日』(当初は『旬刊朝日』)創刊に参加。東京勤務を経て、昭和11年/1936年から「朝日会館」主事となる。
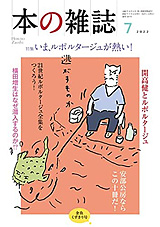
『本の雑誌』
令和4年/2022年7月号
(6月発売号)
令和4年/2022年7月号
(6月発売号)
第5回
庶民に目線を合わせた人たち
伊藤みはる(都新聞)
明治11年/1878年
~大正10年/1921年2月6日(享年43)
本名・万三郎。東京出身。~大正10年/1921年2月6日(享年43)
陸軍輜重兵軍曹として日露戦争に従軍。その後『東京新報』を経て明治41年/1908年頃『都新聞』に入社。艶ダネ記者として活躍するかたわら、大日本雄弁会講談社『講談倶楽部』の執筆陣に加わる。
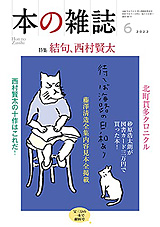
『本の雑誌』
令和4年/2022年6月号
(5月発売号)
令和4年/2022年6月号
(5月発売号)
第4回
文学に踏み止まらない人
柴田勝衛(時事新報、読売新聞)
明治21年/1888年6月4日
~昭和46年/1971年1月16日(享年82)
宮城県仙台市生まれ。青山学院高等科卒。~昭和46年/1971年1月16日(享年82)
教文館勤務を経て、明治45年/1912年『時事新報』に入社。文芸記者として存在感を見せ、大正8年/1919年、同社の千葉亀雄とともに『読売新聞』に移籍。のち文芸部長、編集局長などを歴任する。

『本の雑誌』
令和4年/2022年5月号
(4月発売号)
令和4年/2022年5月号
(4月発売号)
第3回
怒られ通し
森田草平(東京朝日新聞)
明治14年/1881年3月19日
~昭和24年/1949年12月14日(享年68)
岐阜県鷺山村生まれ。東京帝国大学英文科卒。~昭和24年/1949年12月14日(享年68)
夏目漱石門下の一人。明治42年/1909年、平塚明子(のち「らいてう」)と心中未遂事件を起こす。同年『東京朝日新聞』に「煤煙」を連載、翌年、漱石が同紙で始めた文芸欄の、編集担当を任される。
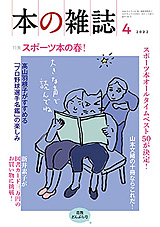
『本の雑誌』
令和4年/2022年4月号
(3月発売号)
令和4年/2022年4月号
(3月発売号)
第2回
振り回される人
嶋田青峰(国民新聞)
明治15年/1882年3月8日
~昭和19年/1944年5月31日(享年62)
本名・賢平。三重県的矢村生まれ。早稲田大学英文科卒。~昭和19年/1944年5月31日(享年62)
学校教師を経て明治41年/1908年、『国民新聞』に入社。高浜虚子のもとで文芸欄を担当し、のち文芸部長となる。その間、虚子に乞われて『ホトトギス』の編集にも参画。大正15年/1926年から俳句誌『土上』主宰。
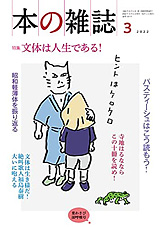
『本の雑誌』
令和4年/2022年3月号
(2月発売号)
令和4年/2022年3月号
(2月発売号)
第1回
論争と黒子の男
堀紫山(読売新聞)
文久3年/1863年10月23日
~昭和15年/1940年3月16日(享年76)
本名・成之。常陸国下館生まれ。栃木県師範学校卒。~昭和15年/1940年3月16日(享年76)
尾崎紅葉門下の第一号。明治23年/1890年、紅葉と共同生活を送り、その頃から『読売新聞』で働く。その後、『大阪朝日新聞』『読売新聞』(復社)『中央新聞』『二六新報』等を転々とする。