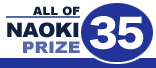直木賞が、(株)文藝春秋の作品に多めに授賞するのは、異状ではない。
あとは程度の問題だ。
あとは程度の問題だ。
直木賞を主催する団体を、公益財団法人日本文学振興会という。名称は公的機関っぽいが、今さら指摘するまでもなく、株式会社文藝春秋の“外郭団体”と言っていい。
平成18年/2006年7月16日現在、同財団のホームページには平成17年/2005年7月1日現在の役員名簿が掲載されているが、理事長は(株)文藝春秋の上野徹社長、 常務理事は同社の斎藤禎常務とあり、役員の顔ぶれだけを見て組織をうんぬんするのは、はしたないことなんだろうけど、まあ、“外郭団体”であることに異論はないだろう。
そもそも、芥川賞・直木賞を創設したのが文藝春秋社主・菊池寛なのはご存知のとおり。昭和10年/1935年の第1回以降、賞の運営は文藝春秋でやっていたのが、 「万が一会社がつぶれても賞だけは継続して残っていってほしい」との思いから、昭和13年/1938年、賞の運営のためだけに、わざわざこの財団を設立したという経緯があるわけだし (芥川賞・直木賞のため、というより、自分の名を冠した菊池寛賞の創設を期して、と言ったほうが適切だろうけども)。
要は、直木賞が、(株)文藝春秋に有利に働くのは、もう当たり前なんだ。誰がどうわめこうと。 「もっと公平に選べよ」と口を酸っぱくして言ったところで、無理なんだ。
そんなこたあ、わかっている。十分承知している。ワタクシのような、直木賞を知ってほんの十数年の若造がわかっているぐらいなのだから、 そりゃあ、ライバル会社の新潮社の人も、講談社の人も、直木賞のことを取り上げる朝日新聞の人も読売新聞の人もNHKの人も、 実際に受賞作を選ぶ選考委員の人たちも、もう重々わかっているはずなんだ。
だから、この小研究のページで、「どうして文藝春秋の作品ばかり選ばれるんだよッ。おかしいじゃないかッ」と怒るのはやめたい。
と自制した上で、でもさあ、直木賞って、どのくらい文藝春秋の作品ばっか選んできたんだろうか、と調べてみたくなった。で、下のバーコードみたいなグラフのようになるわけだ。
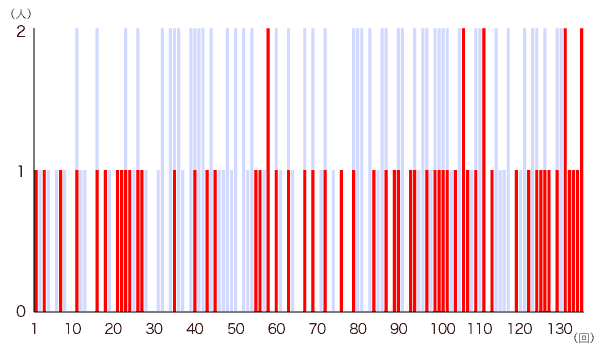
※赤い棒が、(株)文藝春秋の作品で受賞した人数(同社が出版する雑誌に掲載されたものや、単行本)、青い棒がその他で受賞した人数
へえ、1回に2人が同時受賞するのって、そんなに特別なことじゃないけど、それが普通になったのは第30回を過ぎた辺りからだったんだ。なんて、今回の趣旨とは関係のない 発見もあるわけだけど、それは別として。今回このようにグラフにしてみたのには訳がある。それは、
●「なんとなく、そう感じる」という話の展開にはしたくなかった。
●「最近、コレコレコウイウ傾向があるって言っても、それってたまたまでしょ?」という反論を防ぎたかった。
以上2つの理由による。
赤い棒が密集している時期は、3つある。1つは、第20回~30回までの間、 2つめは、第90回から100回を過ぎた辺り、 そして3つめは、第120回台後半から今、なんだ。これが文春の作品が比較的数多く直木賞をとっている時期を指している。 おそらくバランス感覚をお持ちの多くの読書好きが、「なんだかヘンだぞ」と直木賞に対して、今、不信の念を抱くのは、 ゆえなきことではない。
過去5度しかない、文春作品が2作同時受賞した例のうち、4度が第100回を過ぎて以降に起こっている、というのも、 目を引く。135回の長き歴史のなかで、100回までに1度しかなかったことが、101回からの35回で4度も起こる、というのは、 そういう視点で見れば異状に見える。
ワタクシの個人的な見解からすれば、第30回~90回ぐらいまでの、(株)文藝春秋を前面に出さない慎ましやかな直木賞の姿勢が好きだ。 今後はそうなっていってほしいと思っている。なにも、(株)文藝春秋の作品を絶対に選ぶな、とは思わない。 直木賞は文春の営業活動の一環としての役割も担っているのだと思うので、 まあ、ほかの出版社より多めに受賞作が生まれても、何も文句はない。しかしそれが度を過ぎると(つまり今みたいな状態まで行くと)品がない。 あさましい。みにくい。みえみえだ。みっともない。そんな直木賞にはなってほしくない。
慎ましやかな頃だって、直木賞は、(株)文藝春秋以外のところから、すばらしい新人・中堅作家を選び出し、 世に送り出しているじゃないですか。それが、今の直木賞が持っている“権威”だの“信頼”だのへと育っていった一因だと思うのだが。 のちに大作家となった面々、戸川幸夫(第32回受賞作は『大衆文藝』誌掲載)、 新田次郎(第34回受賞作は朋文堂刊)、 山崎豊子(第39回受賞作は中央公論社刊)、 平岩弓枝(第41回受賞作は『大衆文藝』誌掲載)、 司馬遼太郎(第42回受賞作は講談社刊)、 山口瞳(第48回受賞作は『婦人画報』誌連載)、 永井路子(第52回受賞作は光風社刊)その他多くの作家が、もちろん当時は新人で、 しかも文春以外のところで活躍していた人たちじゃないですか。
目先の利益にとらわれつつも、でもそうじゃないところにも目を配れる、そんな直木賞に、早く戻ってほしい。上のグラフをつくってみて、 ワタクシは改めて強くそう思ったわけだ。
P.L.B.
平成18年/2006年7月16日現在、同財団のホームページには平成17年/2005年7月1日現在の役員名簿が掲載されているが、理事長は(株)文藝春秋の上野徹社長、 常務理事は同社の斎藤禎常務とあり、役員の顔ぶれだけを見て組織をうんぬんするのは、はしたないことなんだろうけど、まあ、“外郭団体”であることに異論はないだろう。
そもそも、芥川賞・直木賞を創設したのが文藝春秋社主・菊池寛なのはご存知のとおり。昭和10年/1935年の第1回以降、賞の運営は文藝春秋でやっていたのが、 「万が一会社がつぶれても賞だけは継続して残っていってほしい」との思いから、昭和13年/1938年、賞の運営のためだけに、わざわざこの財団を設立したという経緯があるわけだし (芥川賞・直木賞のため、というより、自分の名を冠した菊池寛賞の創設を期して、と言ったほうが適切だろうけども)。
要は、直木賞が、(株)文藝春秋に有利に働くのは、もう当たり前なんだ。誰がどうわめこうと。 「もっと公平に選べよ」と口を酸っぱくして言ったところで、無理なんだ。
そんなこたあ、わかっている。十分承知している。ワタクシのような、直木賞を知ってほんの十数年の若造がわかっているぐらいなのだから、 そりゃあ、ライバル会社の新潮社の人も、講談社の人も、直木賞のことを取り上げる朝日新聞の人も読売新聞の人もNHKの人も、 実際に受賞作を選ぶ選考委員の人たちも、もう重々わかっているはずなんだ。
だから、この小研究のページで、「どうして文藝春秋の作品ばかり選ばれるんだよッ。おかしいじゃないかッ」と怒るのはやめたい。
と自制した上で、でもさあ、直木賞って、どのくらい文藝春秋の作品ばっか選んできたんだろうか、と調べてみたくなった。で、下のバーコードみたいなグラフのようになるわけだ。
第1回~135回の直木賞受賞者数(文藝春秋とその他別)
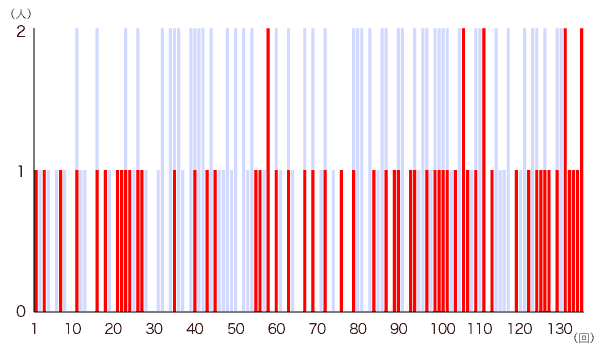
※赤い棒が、(株)文藝春秋の作品で受賞した人数(同社が出版する雑誌に掲載されたものや、単行本)、青い棒がその他で受賞した人数
へえ、1回に2人が同時受賞するのって、そんなに特別なことじゃないけど、それが普通になったのは第30回を過ぎた辺りからだったんだ。なんて、今回の趣旨とは関係のない 発見もあるわけだけど、それは別として。今回このようにグラフにしてみたのには訳がある。それは、
●「なんとなく、そう感じる」という話の展開にはしたくなかった。
●「最近、コレコレコウイウ傾向があるって言っても、それってたまたまでしょ?」という反論を防ぎたかった。
以上2つの理由による。
赤い棒が密集している時期は、3つある。1つは、第20回~30回までの間、 2つめは、第90回から100回を過ぎた辺り、 そして3つめは、第120回台後半から今、なんだ。これが文春の作品が比較的数多く直木賞をとっている時期を指している。 おそらくバランス感覚をお持ちの多くの読書好きが、「なんだかヘンだぞ」と直木賞に対して、今、不信の念を抱くのは、 ゆえなきことではない。
過去5度しかない、文春作品が2作同時受賞した例のうち、4度が第100回を過ぎて以降に起こっている、というのも、 目を引く。135回の長き歴史のなかで、100回までに1度しかなかったことが、101回からの35回で4度も起こる、というのは、 そういう視点で見れば異状に見える。
ワタクシの個人的な見解からすれば、第30回~90回ぐらいまでの、(株)文藝春秋を前面に出さない慎ましやかな直木賞の姿勢が好きだ。 今後はそうなっていってほしいと思っている。なにも、(株)文藝春秋の作品を絶対に選ぶな、とは思わない。 直木賞は文春の営業活動の一環としての役割も担っているのだと思うので、 まあ、ほかの出版社より多めに受賞作が生まれても、何も文句はない。しかしそれが度を過ぎると(つまり今みたいな状態まで行くと)品がない。 あさましい。みにくい。みえみえだ。みっともない。そんな直木賞にはなってほしくない。
慎ましやかな頃だって、直木賞は、(株)文藝春秋以外のところから、すばらしい新人・中堅作家を選び出し、 世に送り出しているじゃないですか。それが、今の直木賞が持っている“権威”だの“信頼”だのへと育っていった一因だと思うのだが。 のちに大作家となった面々、戸川幸夫(第32回受賞作は『大衆文藝』誌掲載)、 新田次郎(第34回受賞作は朋文堂刊)、 山崎豊子(第39回受賞作は中央公論社刊)、 平岩弓枝(第41回受賞作は『大衆文藝』誌掲載)、 司馬遼太郎(第42回受賞作は講談社刊)、 山口瞳(第48回受賞作は『婦人画報』誌連載)、 永井路子(第52回受賞作は光風社刊)その他多くの作家が、もちろん当時は新人で、 しかも文春以外のところで活躍していた人たちじゃないですか。
目先の利益にとらわれつつも、でもそうじゃないところにも目を配れる、そんな直木賞に、早く戻ってほしい。上のグラフをつくってみて、 ワタクシは改めて強くそう思ったわけだ。
P.L.B.