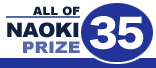純文学とか大衆文学とか、そんな区分けは
しょせん大して意味のあることではありません。
小説は小説。それ以上の細ごました分類なんてしゃらくせえぜ。
まったく仰せのとおり。
しかし、日本の小説界にこれら二つの概念が歴然と
存在していたこと(していること)は、事実です。
もっと言えば、直木賞の歴史の背骨には、
いかに“馬鹿にされない大衆文学になるか”という闘いが
長い間貫かれていました。
その中で直木賞史上に名前を残すことになった
“純文学畑”の作家を取り上げていきます。
今回は、左翼運動からいくつかの同人誌を経て、
終戦まもなくシベリア抑留中に亡くなった、
岩手出身の気骨のひと、古澤元です。
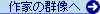 古澤元 候補作家の群像
古澤元 候補作家の群像
しょせん大して意味のあることではありません。
小説は小説。それ以上の細ごました分類なんてしゃらくせえぜ。
まったく仰せのとおり。
しかし、日本の小説界にこれら二つの概念が歴然と
存在していたこと(していること)は、事実です。
もっと言えば、直木賞の歴史の背骨には、
いかに“馬鹿にされない大衆文学になるか”という闘いが
長い間貫かれていました。
その中で直木賞史上に名前を残すことになった
“純文学畑”の作家を取り上げていきます。
今回は、左翼運動からいくつかの同人誌を経て、
終戦まもなくシベリア抑留中に亡くなった、
岩手出身の気骨のひと、古澤元です。
昭和15年/1940年、大衆文学作家にまじって候補に挙がった見慣れぬ名前。
第12回直木賞。昭和15年/1940年下半期。候補者として村上元三、岩下俊作、長谷川幸延など、戦前の大衆文学界でおなじみ感のある名前が並ぶ中、ちょっと見慣れない作家名、雑誌名の候補が挙がっている。古澤元。候補作は「紀文抄」。発表誌は『麦』。
『麦』といって、ああアレかとすんなりうなずいて次を読み進もうと思ったあなたの、足元にも及ばないほどの知識しかワタクシにはないが、簡単に紹介すると『麦』は昭和15年/1940年に創刊された同人誌で、同人に倉光俊夫、池田源尚、朝山洋太郎、そして古澤元がいる。倉光はのち「連絡員」で芥川賞を受賞、池田は「運・不運」で文藝賞を受賞するなどの実力派揃いだが、それまでの直木賞が主に『オール讀物』などに掲載された作品を候補作にしてきたことを考えると、おや、どうしてこの雑誌の作品が候補に? と思うのが自然だろう。
古澤元といって、ああアノ人かとすんなりうなずいて次を読み進もうと思ったあなたの、足元にも及ばない……ってくどい。古澤は昭和3年/1928年、仙台の旧制二高を放校処分となり、上京してプロレタリア文学誌『戦旗』編集部で働く身となる。武田麟太郎に師事し、『日暦』『人民文庫』『麦』『正統』の同人として小説・評論などを発表。戦時中には武田の紹介で、右翼の大物、橋本欣五郎の下で働くが、昭和20年/1945年に満洲に応召。終戦後シベリアに抑留され、抑留地で39年の生涯を閉じた。
遺した作品は多くはない。それどころか今、新刊書店に出向いても、まず彼の作品にお目にかかることはできない。まちの図書館まで範囲を広げても事情はほぼ同じだ。ましてや候補作の「紀文抄」を読もうと思っても、いったいどこを探せばいいというのだ。
ワタクシは不勉強なうえに、俗にいう大衆文学にばかり興味があるものだから、『日暦』『人民文庫』の作家といわれてもピンとこないが、それでも大衆文学作家にまじってひときわ目立つ聞きなじみのない存在感とか、選評で白井喬二や宇野浩二が高い評価を与えている直木賞候補作となれば、読んでみたい思いがうずうずと沸いてくるわけだ。
『麦』といって、ああアレかとすんなりうなずいて次を読み進もうと思ったあなたの、足元にも及ばないほどの知識しかワタクシにはないが、簡単に紹介すると『麦』は昭和15年/1940年に創刊された同人誌で、同人に倉光俊夫、池田源尚、朝山洋太郎、そして古澤元がいる。倉光はのち「連絡員」で芥川賞を受賞、池田は「運・不運」で文藝賞を受賞するなどの実力派揃いだが、それまでの直木賞が主に『オール讀物』などに掲載された作品を候補作にしてきたことを考えると、おや、どうしてこの雑誌の作品が候補に? と思うのが自然だろう。
古澤元といって、ああアノ人かとすんなりうなずいて次を読み進もうと思ったあなたの、足元にも及ばない……ってくどい。古澤は昭和3年/1928年、仙台の旧制二高を放校処分となり、上京してプロレタリア文学誌『戦旗』編集部で働く身となる。武田麟太郎に師事し、『日暦』『人民文庫』『麦』『正統』の同人として小説・評論などを発表。戦時中には武田の紹介で、右翼の大物、橋本欣五郎の下で働くが、昭和20年/1945年に満洲に応召。終戦後シベリアに抑留され、抑留地で39年の生涯を閉じた。
遺した作品は多くはない。それどころか今、新刊書店に出向いても、まず彼の作品にお目にかかることはできない。まちの図書館まで範囲を広げても事情はほぼ同じだ。ましてや候補作の「紀文抄」を読もうと思っても、いったいどこを探せばいいというのだ。
ワタクシは不勉強なうえに、俗にいう大衆文学にばかり興味があるものだから、『日暦』『人民文庫』の作家といわれてもピンとこないが、それでも大衆文学作家にまじってひときわ目立つ聞きなじみのない存在感とか、選評で白井喬二や宇野浩二が高い評価を与えている直木賞候補作となれば、読んでみたい思いがうずうずと沸いてくるわけだ。
幻の候補作「紀文抄」を復元させた郷土の熱意。

『古澤元作品集』
平成18年/2006年3月・
沢内村教育委員会刊
~内容~
「発刊にあたって 沢内村教育長 高橋稔」 「発刊に感謝 沢内村長 高橋繁」 「『古澤元作品集』―刊行に寄せて― 監修 吉見正信」 「だしそこねた手紙」 「創作短編「秋」 秦 巳三雄」 「汽笛(ホイッスル)」 「馬を賣る日」 「木苺の実」 「めくれこんだ批評―島木健作作品評―」 「さはがに」 「紀文抄」 「病気 その他」 「家鼠」 「バルザックの方法」 「外濠端」 「文藝正統~私小説論と井戸端会議」 「水戸に学ぶ―歴史小説雑記―」 「文藝月評」 「有厄」 「文藝正統~同人募集に反対す」 「文藝月評(二)」 「文藝月評(三)」 「文藝正統~同人雑誌「正統」について」 「文藝正統~小説に対する疑惑」 「文藝正統~友情と文学」 「文藝正統~続・小説に対する疑惑」 「議事堂」 「辻小説 惣平」 「熱河省境」 「文藝正統~「八誌統合」を反駁する」 「文藝正統~同人雑誌廃刊雑記―文学的千早城を築かう」 「年の輪」 「常道を往く」 「第一歩―模索する心で―」 「父の蔵書物語 古澤 襄」 「古澤元の生涯 吉見正信」 「古澤元関係略年譜」 「あとがき 加藤宏泰」 「岸丈夫 年譜」 「岸丈夫漫画作品」
「発刊にあたって 沢内村教育長 高橋稔」 「発刊に感謝 沢内村長 高橋繁」 「『古澤元作品集』―刊行に寄せて― 監修 吉見正信」 「だしそこねた手紙」 「創作短編「秋」 秦 巳三雄」 「汽笛(ホイッスル)」 「馬を賣る日」 「木苺の実」 「めくれこんだ批評―島木健作作品評―」 「さはがに」 「紀文抄」 「病気 その他」 「家鼠」 「バルザックの方法」 「外濠端」 「文藝正統~私小説論と井戸端会議」 「水戸に学ぶ―歴史小説雑記―」 「文藝月評」 「有厄」 「文藝正統~同人募集に反対す」 「文藝月評(二)」 「文藝月評(三)」 「文藝正統~同人雑誌「正統」について」 「文藝正統~小説に対する疑惑」 「文藝正統~友情と文学」 「文藝正統~続・小説に対する疑惑」 「議事堂」 「辻小説 惣平」 「熱河省境」 「文藝正統~「八誌統合」を反駁する」 「文藝正統~同人雑誌廃刊雑記―文学的千早城を築かう」 「年の輪」 「常道を往く」 「第一歩―模索する心で―」 「父の蔵書物語 古澤 襄」 「古澤元の生涯 吉見正信」 「古澤元関係略年譜」 「あとがき 加藤宏泰」 「岸丈夫 年譜」 「岸丈夫漫画作品」
インターネットで「古澤元」を検索していたら、古澤襄という方が主宰する「杜父魚文庫」やそのブログにたどりついた。古澤襄さんは、まさしく古澤元のご子息である。共同通信社で記者として活躍、常務理事まで経験されたのち、今では数々のご著書をもち、インターネット上でも数多くの文章を発表されている。その中には父・古澤元に触れたものがいくつもあり、ワタクシは氏の文章ではじめて、古澤元が岩手県沢内村の出身であり、第8回直木賞受賞の大池唯雄と、旧制高校時代以来の友人であったことなどを知った。
さらに見ていくと、岩手県沢内村が町村合併で西和賀町になることを機に、郷土の作家である古澤元の作品を集めた『古澤元作品集』が、平成18年/2006年に刊行されていたことがわかった。ここに、これまで容易に読むことのできなかった「紀文抄」も収められているという。うおう、読んでみたいぞ。たまらずワタクシは、古澤襄さん宛てにメールを出してしまった。
すぐに襄さんから返信があった。大変丁寧な内容で、古澤元に関してさまざまな事柄をご教示いただいたうえに、さらには顔も知らぬ、どこの馬の骨とも知らぬ偏屈なシロウト直木賞研究家(ワタクシのことです)のために、『古澤元作品集』や、古澤元に関する本をお送りいただいた。感激感涙のいたりだった。いつしか「紀文抄」を読むことはワタクシの長年の夢となっていたが、ついにそれが果たせた晩は、至福の思いで眠りにつくことができた。古澤襄さん、ほんとうにありがとうございます。
直木賞のことを知りたい、と思う人よりは、おそらくずっとずっと数が多いと思われるプロレタリア文学研究者や戦時下における同人誌の研究者などにとっても、きっと貴重で参考になる文献だと想像し、とりあえず目次の内容だけでもと思って左に挙げておいた。
さらに見ていくと、岩手県沢内村が町村合併で西和賀町になることを機に、郷土の作家である古澤元の作品を集めた『古澤元作品集』が、平成18年/2006年に刊行されていたことがわかった。ここに、これまで容易に読むことのできなかった「紀文抄」も収められているという。うおう、読んでみたいぞ。たまらずワタクシは、古澤襄さん宛てにメールを出してしまった。
すぐに襄さんから返信があった。大変丁寧な内容で、古澤元に関してさまざまな事柄をご教示いただいたうえに、さらには顔も知らぬ、どこの馬の骨とも知らぬ偏屈なシロウト直木賞研究家(ワタクシのことです)のために、『古澤元作品集』や、古澤元に関する本をお送りいただいた。感激感涙のいたりだった。いつしか「紀文抄」を読むことはワタクシの長年の夢となっていたが、ついにそれが果たせた晩は、至福の思いで眠りにつくことができた。古澤襄さん、ほんとうにありがとうございます。
直木賞のことを知りたい、と思う人よりは、おそらくずっとずっと数が多いと思われるプロレタリア文学研究者や戦時下における同人誌の研究者などにとっても、きっと貴重で参考になる文献だと想像し、とりあえず目次の内容だけでもと思って左に挙げておいた。
直木賞が試みたいくつかの改革。
「紀文抄」は、江戸の材木商人・紀伊国屋文左衛門の、豪遊生活を送っていた日常を、文左衛門の心理を追うことで描いた作品だ。むろんワタクシなぞに評論する力はないので、評論はしない。読んでわかるのは、同じ時代小説(古澤のは歴史小説と言ったほうが近いかも)でも、直木賞を争った村上元三などの作品に比べて明らかに異質ということだ。登場人物の心理を丹念に深くまでえぐっていく書き方が異質だし、とりわけ文体が異質だ。
おそらく芥川賞あたりの舞台で取り上げられたほうが、まだしもしっくり来るが、いやいや待てよ、この作品が直木賞の候補作となったところに、ワタクシは当時の直木賞の「大衆文学の地位を向上させる」闘いを見てみたい。
そもそも創設以来、芥川賞・直木賞、と並び称されてはいるが、直木賞って芥川賞よりも格が下だよねという雰囲気のあったことは、どうしても免れ得ない。
はじまった頃の両賞を事務方として支えた永井龍男の『回想の芥川・直木賞』にも、はっきりとこう書いてある。
軽く見る態度とはまったく違うが、小島政二郎は第9回の選評で、直木賞委員に対して不満をぶちまけている。
それで業を煮やした主催者当局のとった手段が実に思い切っていて、第11回からは芥川賞の全委員に直木賞委員も兼ねさせる(その逆でないことに注意されたい)という奇策に打って出る。
さらにいえば、この頃試みられた新しい方向性がもう一つある、とワタクシは推察する。それは『オール讀物』『大衆文藝』『サンデー毎日』『新青年』といった商業の娯楽誌ばかりでなく、同人誌からも候補となり得る作品を探そうとする姿勢だった。おそらく、その先鞭は第10回のときに『九州文学』から探し当ててきた岩下俊作「富島松五郎伝」である。この方向性が第12回の候補リストに「紀文抄」を加えるもとになったのではないだろうか。
「読んで面白いだけではダメで、そこに“文学”がないと直木賞には値しない」などと不毛とも思えるハナシが、今だって直木賞選考の場では根強く語られたりするけれども、人間は、どんなことにも意味や理由を見出さないと堪えられない厄介な生き物らしい。戦前の直木賞もやはりこの厄介さにしばられていて、その一端が第10回以降のいくつかの改革に結びついていく。要は「大衆文学なんてなんら評価に値しないくだらぬものだ」という偏見を打破すべく、純文学の畑から少しでもエキスを拝借して、大衆文学もいやあ立派な文学になりましたねと言ってもらえるようなものにしていきたい、という動きだ。
ただし、残念ながらこの改革はあまり長く続かなかった。芥川賞委員の兼任は第13回を最後に早々に打ち切られているようだし、このあと戦前の候補作リストをたどっていってみても、結局そのほとんどが前記の商業誌(プラス『講談倶楽部』)に掲載されたものに終始している。
そんなに単純に純文学を直木賞の場に取り込むことはできないんだなと悟ったのかもしれない。もちろん書きたいものが自由に書けなくなっていき、評価したいものを自由に評価できなくなった時代のせいもあるだろう。戦時下の直木賞の変貌については、このページで語るテーマではないので、また別の機会に考えてみたいと思う。
おそらく芥川賞あたりの舞台で取り上げられたほうが、まだしもしっくり来るが、いやいや待てよ、この作品が直木賞の候補作となったところに、ワタクシは当時の直木賞の「大衆文学の地位を向上させる」闘いを見てみたい。
そもそも創設以来、芥川賞・直木賞、と並び称されてはいるが、直木賞って芥川賞よりも格が下だよねという雰囲気のあったことは、どうしても免れ得ない。
はじまった頃の両賞を事務方として支えた永井龍男の『回想の芥川・直木賞』にも、はっきりとこう書いてある。
初期には、芥川賞委員で直木賞委員を兼ねた人が数名あることは、前に記録した通りだが、その逆というのはない。
当時の文壇の主流が純文学に占められていた証左で、銓衡会席上にもおのずとその雰囲気がただよい、
直木賞単独の委員の発言には、一目置いたところがあったのは否めない。
また両賞委員を兼ねた人々の中に、直木賞委員を軽く見る態度のほの見えた事実もしばしば私は経験した。
創設期の両賞兼任委員は、菊池寛、佐佐木茂索、久米正雄、小島政二郎の4名。永井は続く段落で、
その間、文藝春秋社側として出席した佐佐木茂索が、両賞兼任委員として公平な立場を持しているのは、今日その選評によっても知られる。
と書いているから、「直木賞委員を軽く見る態度」をほの見せたのが誰だったのかは、けっこう絞られてくる。軽く見る態度とはまったく違うが、小島政二郎は第9回の選評で、直木賞委員に対して不満をぶちまけている。
内輪から火事を出すようで甚だ宜しくないが、直木賞の委員諸君、どうかもう少し出席して下さい。私だって決して勉強家の方ではないが、それでも出席だけは必ずしている。出席して、芥川賞の委員のように甲論乙駁、議論を上下しようではないか。
(中略)
「どうも熱心が足らん」
そう云われる度に、私は切ないのだ。直木賞の銓衡に熱心とか不熱心とか云うことでなしに、文学に対する熱心不熱心を云われているような気がして、何か鼎の軽重を問われている見たいな思いがするのだ。
ちなみに当時の直木賞「単独委員」は、吉川英治、大佛次郎、三上於菟吉、白井喬二の4名である。(中略)
「どうも熱心が足らん」
そう云われる度に、私は切ないのだ。直木賞の銓衡に熱心とか不熱心とか云うことでなしに、文学に対する熱心不熱心を云われているような気がして、何か鼎の軽重を問われている見たいな思いがするのだ。
それで業を煮やした主催者当局のとった手段が実に思い切っていて、第11回からは芥川賞の全委員に直木賞委員も兼ねさせる(その逆でないことに注意されたい)という奇策に打って出る。
さらにいえば、この頃試みられた新しい方向性がもう一つある、とワタクシは推察する。それは『オール讀物』『大衆文藝』『サンデー毎日』『新青年』といった商業の娯楽誌ばかりでなく、同人誌からも候補となり得る作品を探そうとする姿勢だった。おそらく、その先鞭は第10回のときに『九州文学』から探し当ててきた岩下俊作「富島松五郎伝」である。この方向性が第12回の候補リストに「紀文抄」を加えるもとになったのではないだろうか。
「読んで面白いだけではダメで、そこに“文学”がないと直木賞には値しない」などと不毛とも思えるハナシが、今だって直木賞選考の場では根強く語られたりするけれども、人間は、どんなことにも意味や理由を見出さないと堪えられない厄介な生き物らしい。戦前の直木賞もやはりこの厄介さにしばられていて、その一端が第10回以降のいくつかの改革に結びついていく。要は「大衆文学なんてなんら評価に値しないくだらぬものだ」という偏見を打破すべく、純文学の畑から少しでもエキスを拝借して、大衆文学もいやあ立派な文学になりましたねと言ってもらえるようなものにしていきたい、という動きだ。
ただし、残念ながらこの改革はあまり長く続かなかった。芥川賞委員の兼任は第13回を最後に早々に打ち切られているようだし、このあと戦前の候補作リストをたどっていってみても、結局そのほとんどが前記の商業誌(プラス『講談倶楽部』)に掲載されたものに終始している。
そんなに単純に純文学を直木賞の場に取り込むことはできないんだなと悟ったのかもしれない。もちろん書きたいものが自由に書けなくなっていき、評価したいものを自由に評価できなくなった時代のせいもあるだろう。戦時下の直木賞の変貌については、このページで語るテーマではないので、また別の機会に考えてみたいと思う。
妻・真喜の伝記から、候補当時の古澤元の様子を垣間見てみる。

『幻の碧き湖
古澤真喜の生涯』
一ノ瀬 綾
平成4年/1992年5月・
筑摩書房刊
~内容~
「碧き湖」(詩) 「幻の碧き湖」 「あとがき」 「参考文献」
「碧き湖」(詩) 「幻の碧き湖」 「あとがき」 「参考文献」
古澤襄さんからいただいた資料の数々を読んでいると、戦前の作家たちの生きざまが見えてきて、だんだんと自分の知り合いのように親近感がわいてきて面白い。
一ノ瀬綾『幻の碧き湖』(平成4年/1992年5月・筑摩書房刊)は、古澤元の妻、古澤真喜の視点から彼女の生涯を描いた伝記小説である。研究書ではなく小説だから、非常に感情移入しやすく、昭和初期から戦時下の古澤夫妻の逼迫した生活ぶりなどは胸にせまるものがある。
むろん小説として読むべきで、書かれていることがすべて事実だと認めてはいけないのだろうけど、古澤元が自分の進むべき道、書くべきものを模索するさま、また同人誌仲間だった高見順などがいちはやく文壇に認められてゆく中で、貧しい生活を余儀なくされていることからくる焦燥や苦渋の姿が書かれている。
「紀文抄」が直木賞候補になったのはちょうどその頃だった。
一ノ瀬綾『幻の碧き湖』(平成4年/1992年5月・筑摩書房刊)は、古澤元の妻、古澤真喜の視点から彼女の生涯を描いた伝記小説である。研究書ではなく小説だから、非常に感情移入しやすく、昭和初期から戦時下の古澤夫妻の逼迫した生活ぶりなどは胸にせまるものがある。
むろん小説として読むべきで、書かれていることがすべて事実だと認めてはいけないのだろうけど、古澤元が自分の進むべき道、書くべきものを模索するさま、また同人誌仲間だった高見順などがいちはやく文壇に認められてゆく中で、貧しい生活を余儀なくされていることからくる焦燥や苦渋の姿が書かれている。
「紀文抄」が直木賞候補になったのはちょうどその頃だった。
『麦』が注目される中、その九月号に発表した古澤元の小説「紀文抄」が、下半期の直木賞候補に挙げられた。周囲は色めきたった。
「大丈夫、絶対いける」
「いやいや、発表になるまでは……」
騒がしい仲間の取沙汰をよそに、本人の元は浮かぬ顔だった。
「あの小説がなぜ直木賞の対象になるんだ。芥川賞こそふさわしいのに……」
本人の不満は分ったが、真喜は世間の誤解を招きかねない言葉に胸を突かれた。本人が納得できないことを、「直木賞でもいいじゃないですか、 長い間の苦労が認められたんですもの……」などとは言えなかった。
何行か中略させていただいて、いよいよ選考会を迎える。
「大丈夫、絶対いける」
「いやいや、発表になるまでは……」
騒がしい仲間の取沙汰をよそに、本人の元は浮かぬ顔だった。
「あの小説がなぜ直木賞の対象になるんだ。芥川賞こそふさわしいのに……」
本人の不満は分ったが、真喜は世間の誤解を招きかねない言葉に胸を突かれた。本人が納得できないことを、「直木賞でもいいじゃないですか、 長い間の苦労が認められたんですもの……」などとは言えなかった。
だがいつしか噂は一人歩きしていた。
「古澤元は直木賞が不満で、受賞しても辞退すると言ったそうな……」
そんな囁きが本人の耳に伝わって来る頃には、選考結果が発表になっていた。
落選だった。真喜は重苦しい期待から解放されて、ほっとしたが、同時に五体が沈んでいくような虚しさと疲労感におそわれた。
(何もかも、終った……)
そんな気がしてならなかった。「決定前から辞退するなんて、不遜な文句を吐いたせいだ」そんな陰口も耳に入る。だが、夫の元は普段の意地張りをさらに強くして、愚痴一つ洩らすことなく、昂然と眉を上げていた。
「古澤元は直木賞が不満で、受賞しても辞退すると言ったそうな……」
そんな囁きが本人の耳に伝わって来る頃には、選考結果が発表になっていた。
落選だった。真喜は重苦しい期待から解放されて、ほっとしたが、同時に五体が沈んでいくような虚しさと疲労感におそわれた。
(何もかも、終った……)
そんな気がしてならなかった。「決定前から辞退するなんて、不遜な文句を吐いたせいだ」そんな陰口も耳に入る。だが、夫の元は普段の意地張りをさらに強くして、愚痴一つ洩らすことなく、昂然と眉を上げていた。
「芥川賞ならよいが、直木賞ではいらない」。
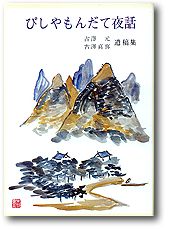
『びしゃもんだて夜話
古澤元・古澤真喜遺稿集』
古澤襄編
昭和57年/1982年3月・
三信図書刊
~内容~
真喜「碧き湖」(詩) 真喜「碧き湖は彼方」 真喜「日記」 元「びしゃもんだて夜話」 元「鶯宿へ」 元「少年」「続少年」 「亡友の写真に思う 大池唯雄」 「古澤元の生涯 吉見正信」 「出会いと作品 池田源尚」 「あとがき 古澤 襄」
真喜「碧き湖」(詩) 真喜「碧き湖は彼方」 真喜「日記」 元「びしゃもんだて夜話」 元「鶯宿へ」 元「少年」「続少年」 「亡友の写真に思う 大池唯雄」 「古澤元の生涯 吉見正信」 「出会いと作品 池田源尚」 「あとがき 古澤 襄」
『文藝春秋』昭和16年/1941年3月号の選評で、「紀文抄」に触れているのは吉川英治、白井喬二、宇野浩二(芥川賞委員兼任)の3人。他の委員や、他の作品に対する評価などの概要は「選評の概要」第12回をご覧いただくとして、ここでは「紀文抄」についての評言を、できるだけ引用してみる。
吉川英治
書いた古澤元本人にしたって「紀文抄」を純文学として評価してもらいたかったのは、おそらく間違いない。先に『幻の碧き湖』からもそんな場面を引用したが、その他にこんな逸話もある。直木賞の候補となったと聞いたとき、「芥川賞ならよいが、直木賞ではいらない」と言い、すでに直木賞作家だった友人の大池唯雄が、ニヤニヤしながらそんな古澤の顔を見ていたそうだ。
古澤元はきっと冥途で、こんな愚にもつかない直木賞専門サイトで自分のことがぐだぐだ紹介されているのを苦々しく思っていることだろう。お許しください、元さん。でもね、直木賞の歩み――ふみこんで解釈すれば、日本の大衆文学と純文学の関係性の歩み――から見れば、古澤元「紀文抄」は、重要な意味をもつ道標なのだと、ワタクシは思うのです。
吉川英治
まず古澤氏の「紀文抄」が審査にのぼったが、わたくしは四篇中この作をもっとも買わなかった。
作家自身もまた純文学を目ざした心構えで書かれたものかと思うが、
それにしても時代観や作中の人物が甚だ薄手で新たに示されているものはない。
ちらと出て来る義士観などにしても一応ずっと以前に唯物史観の人々に云い古された語片が交じっているという感じを出ない。
巧緻な筆致はある。要するに部屋住のひとが窓から閑にまかせて世間のあらを見て批評しているようで世間の実感なり生々しさがない。
もちろん大衆文学の読者には縁遠い性格だし、
なおこの程度では純文学温室で観賞植物として見るにもものたらないのではないかと思われる。
白井喬二
今度の候補作品の内から、僕は「上総風土記」「廟行鎮再び」の順序に選び、別に「麦」という同人雑誌に載った「紀文抄」をも併せ推薦した。
しかし「紀文抄」は作者古澤元氏が純文学のつもりで書いたのだからと云う説も出たし、僕としてもこの作は巧いには巧いが、
表現が古典的といっても好いくらい類型で創造の領域への踏込みが一歩足らないと云う点で、いつでも引っ込めて好いと附言したのだから、
諸氏の賛意はかばかしからざるを見て、僕も潔く断念した。
宇野浩二
『紀文抄』は、直木賞というものを頭に入れなければ、私には、この方が、今度の直木賞候補作品の中で、最も面白かった。
ところが、この小説は、他の銓衡員たちが、終りの方に――仮名世説ヨリ――とあるので、太田南畝の『仮名世説』の中から得た題材であるというので、
私も「それもそうか、」と思って、推奨されなかった。
しかし、私は、後になって考えたのであるが、そういう事に拘らず、この小説は、直木賞の候補より、芥川賞の候補になった方が、と思った。 しかし、これは、固より、後の祭である。
どの選評にも「純文学」やら「芥川賞」やらの文字が登場するのは、先に書いたような主催者側からの改革を、実際に選考する委員諸氏がどう受け止めているかが正直に出ているものと読める。純文学の畑のものを直木賞の舞台で議論しようとしたとき、どうしても「あちらの畑、うちの畑」と、無意識のうちに見えない柵を設けざるを得なかったあらわれなのだろう。柵をとっぱらった上で大衆文学を考えるのは、選考委員たちにとって、そんなに簡単な業ではなかったのだ。しかし、私は、後になって考えたのであるが、そういう事に拘らず、この小説は、直木賞の候補より、芥川賞の候補になった方が、と思った。 しかし、これは、固より、後の祭である。
書いた古澤元本人にしたって「紀文抄」を純文学として評価してもらいたかったのは、おそらく間違いない。先に『幻の碧き湖』からもそんな場面を引用したが、その他にこんな逸話もある。直木賞の候補となったと聞いたとき、「芥川賞ならよいが、直木賞ではいらない」と言い、すでに直木賞作家だった友人の大池唯雄が、ニヤニヤしながらそんな古澤の顔を見ていたそうだ。
古澤元はきっと冥途で、こんな愚にもつかない直木賞専門サイトで自分のことがぐだぐだ紹介されているのを苦々しく思っていることだろう。お許しください、元さん。でもね、直木賞の歩み――ふみこんで解釈すれば、日本の大衆文学と純文学の関係性の歩み――から見れば、古澤元「紀文抄」は、重要な意味をもつ道標なのだと、ワタクシは思うのです。
(平成19年/2007年3月21日記)