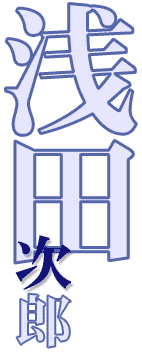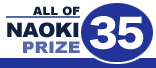
選評の概要
137. 138. 139. 140.141. 142. 143. 144. 145.
146. 147. 148. 149. 150.
151. 152. 153. 154. 155.
156. 157. 158. 159. 160.
161. 162. 163. 164. 165.
166. 167. 168. 169. 170.
171. 172. 173. 174.
| 生没年月日【注】 | 昭和26年/1951年12月13日~ | |
| 在任期間 | 第137回~(通算19年・38回) | |
| 在任年齢 | 55歳6ヶ月~ | |
| 経歴 | 本名=岩戸康次郎。東京都生まれ。中央大学杉並高等学校卒。 | |
| 受賞歴・候補歴 |
|
|
| サブサイトリンク | ||
| 処女作 | 『とられてたまるか!』(平成3年/1991年11月・学習研究社刊) | |
| 直木賞候補歴 | 第115回候補 『蒼穹の昴』(上)(下)(平成8年/1996年4月・講談社刊) 第117回受賞 『鉄道員』(平成9年/1997年4月・集英社刊) |
|
| サイト内リンク | ▼直木賞受賞作全作読破への道Part2 | |
| 備考 | 生年月日および受賞年齢が間違っておりましたので、 平成12年/2000年12月21日訂正いたしました。 お詫び申し上げるとともに、ご指摘いただいた方には 深く感謝いたします。ありがとうございました。 |
|
下記の選評の概要には、評価として◎か○をつけたもの(見方・注意点を参照)、または受賞作に対するもののみ抜粋しました。さらにくわしい情報は、各回の「この回の全概要」をクリックしてご覧ください。
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 新野剛志 | ◎ | 35 | 「平和で豊かな世の中というのも、こと文学にとっては考えもので、小説家は本来文学の核となるべき苦悩を個人的に探し回らねばならない。そうした頽廃の原理に気付き、懸命に現実生活の苦悩をノベライズした作品として、私は(引用者中略)推した。」「小説とは何か、という哲学を修めたうえで、歴史的には笑止千万な現代青年の苦悩を表現したように思えた。」「たぶん作者はこの一作を前菜として、まったく思いがけない料理の用意があると私は考えた。あえて強く推さなかった理由は、その期待感である。」 | |
| □ | 18 | 「伝統的な文学のスタイルを踏襲している」「自然主義の様式に呪縛されたフィクションなので、ダイナミックなストーリー展開がかなわず、かといって内面に踏みこむにも限界がある。しかしそうした基本構造上の矛盾を、文章の力によって静謐な絵に描きおえたのはさすがである。いささか苦言は呈したものの受賞には異論がない。」 | ||
| 「文学の核たるべき苦悩を免れたわれわれが「漠然たる不安」などと言わずにどうすれば小説をなしうるのかと、真剣に考えさせられる選考会であった。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』平成20年/2008年9月号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ○ | 42 | 「美は権力に庇護されるべきか超然として独立するべきかという争点をめぐって、多くの証人が証言台に立つ法廷小説のように私は読んだ。中世美学裁判である。したがって判決は利休の死ではなく、彼を最もよく知る人物によって香合が割られる決着となる。少々深読みが過ぎるであろうか。」「(引用者注:北重人とともに)このさき時代小説の両翼となるのではなかろうか。」 | ||
| 北重人 | ○ | 16 | 「いったいに風景と人物の描写がすぐれており、その特性が一城下を舞台とした連作短篇という設えの中で有効に機能した。」「(引用者注:山本兼一とともに)このさき時代小説の両翼となるのではなかろうか。」 | |
| ■ | 26 | 「いささか苦言を呈した。たしかに苦悩なき世に苦悩する作家的姿勢は貴重だが、作家自身がここまで苦悩に呑みこまれてよいものか、という疑問である。仮にその切実感によって多くの読者の共感を得たとしても、小説本来の効能たる娯楽性をたがいに放棄してしまうのなら、ノンフィクションのほうが理に適っている。つまりあえて物語に仕立てる理由を、見出すことができなかった。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成21年/2009年3月号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 島本理生 | ○ | 16 | 「作品としての完成度には疑問を抱いたが、この作者のうちには「小説とはこういうもの」という法律があるようで、その無意識の心構えが、たとえば礼節を弁えた良家の子女のような居ずまいたたずまいのよさを感じさせた。」「おそらく受賞は力に変わると信じて推奨した。」 | |
| □ | 20 | 「これまでの(引用者注:作者自身の)作品に較べて、明らかにすぐれているのである。こうした考え方には異論もあろうが、少くとも自己の小説世界を着実に積み上げて、その精華というべきこの作品を獲得したという事実は、創作者が範とするべきであり、賞讃に価すると思った。」 | ||
| 「今回は強く推すべき作品が見当らぬまま選考会に臨んだ。」「総じて今回の候補作が、過去の選考会なみの水準に達していたとは思えない。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』平成23年/2011年9月号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ◎ | 28 | 「(引用者注:候補作のなかで)抜きん出ていた。文章に勢いがあり、作者も書くことを楽しんでいるとみえて、まるで本がはね回るような躍動感が漲っていた。」「これだけディテールを積み上げると、メインストーリーが脅かされるものだが、筆が滑るかと思う間にきちんと本題に戻るのは、冷静に長篇の全体像を捉えているからなのだろう。」 | ||
| 西川美和 | ◎ | 10 | 「(引用者注:「流」と共に)一票を投じた。」「垢抜けているのである。既成の文学に縛られず、いわば小説のメソッドに忠実でない自由奔放な作風が痛快であった。」 | |
| 「すこぶる高水準の候補作が並んだ」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』平成27年/2015年9月号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 窪美澄 | ○ | 26 | 「まったくその表題通りに、働けど楽にならざる苦労を描いた佳品である。そのテーマのシンプルさゆえに小説のダイナミズムは欠くのだが、舞台設定が自然で登場人物もよく練られており、完成度はすこぶる高かった。」「おそらく作者には清貧の世界観があるのだろう。そうでなければ、理不尽な苦労をかくも清潔に描けるはずはない。」 | |
| □ | 13 | 「受賞に異論はない。ページを繰るたびに、才能のしずくがこぼれ落ち、香気が立つような気がした。」「それでも本作を強く押せなかった理由は、構造上の疑問であった。このストーリーを一人称で支えるのはつらい。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成30年/2018年9月号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 深緑野分 | ◎ | 28 | 「私は迷わず(引用者中略)推した。」「人物描写がていねいで、風景もまるで細密画を見るようである。」「これだけ密度の濃い小説は今日稀である。」「あえて難を言うなら、以前の候補作と同様にミステリーの結構を持ちこんだことで、本来堂々たる人間劇となるはずの作品を、かえって小さくしてしまったきらいがあった。小説すなわちミステリーとするのは錯誤である。」 | |
| □ | 26 | 「受賞に異論はない。沖縄からすぐれた作家や表現者が生まれるのは、美しい自然に恵まれ、なおかつその美しさにそぐわぬ苦悩を歴史が与えたからであろう。」「出身地を異にする作家が、沖縄の自然を愛し、苦悩の核を胸に抱いた。そして読者はこの小説を通して、知られざる苦悩を知る。」 | ||
| 「今回は常にもまして粒揃いの作品が並ぶ選考会であった」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』平成31年/2019年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 窪美澄 | ○ | 20 | 「迷った末に私が推したものは窪美澄氏「トリニティ」である。」「作者の年齢からすると少し前の時代、私をはじめ選考委員の多くにとっては実体験した時代という設定は相当に難しいはずだが、細部までよく考証がなされていたと思う。そしていつものことながら、作者の紡ぐ苦労譚には説得力がある。フレームストーリーをもう少し生かして、バランスのいい構造になっていれば、と惜しまれた。」 | |
| ■ | 14 | 「推せなかった理由は、ほとほと感心して読みながらも、あまりに大衆文学としての普遍性を欠くと考えたからである。」「いったいどれほどの読者の理解を得られるかと思えば、ためらいが先に立った。」 | ||
| 「どの作品が受賞してもおかしくはない、と思える難しい選考会であった。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和1年/2019年9・10月合併号 |
||||
| 選考委員 浅田次郎 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 一穂ミチ | ◎ | 17 | 「読み始めたとたん、新人ではないと確信した。小説の書き方が手慣れており、かつ垢抜けていて、美学も哲学も備えた文学の構えをしていた。しかも収録された短篇のそれぞれが個性に富み、高い水準を保って出来不出来がなかった。」「私は作者の確固たる文学観と穢れなき才能を信じて強く推した。」 | |
| □ | 15 | 「実直な作家である。」「「星落ちて、なお」は生真面目な作風に手が合っており、すぐれた評伝でも読むような気分で楽しめた。ぜひとも本作で受賞していただきたいと願って選考会に臨んだ。」 | ||
| ■ | 29 | 「(引用者注:選考会で)最も議論がかわされた作品」「これほど壮大で精密な虚構は、小説という表現方法だからこそ可能と思える。だが、その壮大さ精密さを実現するために、視点者の情動が犠牲になった。登場人物のおのおのが、当たり前の人間感情を欠くのである。」「死は文学の欠くべからざるテーマにはちがいないが、死をかくも丹念に描くことはむしろ、人間不在の反文学としか思えなかった。」 | ||
| 「コロナ禍にあって、「小説とは何か」を考え続けた貴重な選考会であったと思う。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和3年/2021年9・10月合併号 |
||||