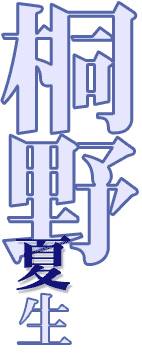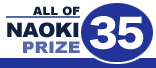
選評の概要
144. 145.146. 147. 148. 149. 150.
151. 152. 153. 154. 155.
156. 157. 158. 159. 160.
161. 162. 163. 164. 165.
166. 167. 168. 169. 170.
171. 172. 173. 174.
| 生没年月日【注】 | 昭和26年/1951年10月7日~ | |
| 在任期間 | 第144回~(通算15.5年・31回) | |
| 在任年齢 | 59歳2ヶ月~ | |
| 経歴 | 本名=橋岡まり子。石川県金沢市生まれ。成蹊大学法学部卒。 | |
| 受賞歴・候補歴 |
|
|
| サブサイトリンク | ||
| 直木賞候補歴 | 第118回候補 『OUT』(平成9年/1997年7月・講談社刊) 第121回受賞 『柔らかな頬』(平成11年/1999年4月・講談社刊) |
|
| サイト内リンク | ▼小研究-ミステリーと直木賞 ▼直木賞受賞作全作読破への道Part1 |
|
下記の選評の概要には、評価として◎か○をつけたもの(見方・注意点を参照)、または受賞作に対するもののみ抜粋しました。さらにくわしい情報は、各回の「この回の全概要」をクリックしてご覧ください。
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 貴志祐介 | ○ | 21 | 「文体もスピードも内容もトーンも、すべてをB級ホラーに徹しようというコンセプトに準じている」「できるようでできない力業であるし、好悪を超えて評価されるべき仕事だと思う。」「表現の自由が狭まりつつある現在、意義ある仕事だと思う。」 | |
| △ | 25 | 「不思議な小説だ。」「登場人物の誰もが、水底の砂のように流れにたゆとうて動こうとはしない。その閉塞感はよく描けている。」「それ故か、定九郎程度の男にどうして、落語の世界、つまり虚構が表す自由、を伝えようとするのかがよくわからなかった。定九郎、花魁、ポン太、それぞれをもっと丁寧に描いていれば、物語全体がよい意味で撓み、力を孕んだであろう。」 | ||
| △ | 21 | 「作者の凄みは、少年の愛と憎しみが、少年を取り巻くすべての人間に向けられていることだ。むしろ、「愛なき世界」の侘びしさでもある。そこが安易な既視感を排除する、太い縦糸となっている。しかし、三人の少年少女の「枠内」を描こうとするあまり、フレーム外の世界が乱暴に省かれたり、都合よく描かれているところが気になる。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成23年/2011年3月号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 島本理生 | ○ | 20 | 「もしかすると、この作品を冗漫だと感じる方も多いかもしれない。トーンが一定していない、と不満に思う人もいるだろう。だが、青春というものはこういう姿をしているのではなかったか、と何度も思った。」「おそらく、大勢の若い女性がこの物語によって救われることだろう。よい小説を読んだ。」 | |
| □ | 31 | 「池井戸さんは、安定した達者な書き手だ。すでに「池井戸ブランド」を確立しておられるし、何も言うことはない。」「面白かったのは、社内の不満が噴き出すあたりだろうか。「夢とプライド」は個人の価値観に過ぎず、会社は、個々の「夢とプライド」を束ねることはできない、ということだ。」「個人的には、主人公と妻の何がどうぶつかって、破局に至ったのかを知りたかった。また、震災後の日本の姿を、是非、池井戸さんに書いて頂きたいと願う。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成23年/2011年9月号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ○ | 23 | 「この作品の白眉は、何と言っても主人公の姉の造型に尽きる。」「(引用者注:主人公の)内省的でシニカル、かつユーモアを孕んだ語り口は、作者がアーヴィングやサリンジャーなどのアメリカ文学に親しんだことがよくわかって楽しい。」「両親の離婚の原因や、幼稚園時代など、蛇足ではないかと感じられる個所もあったが、勢いが感じられる。」 | ||
| 木下昌輝 | ○ | 17 | 「新人とは思えない文章の切れ味と迫力に驚いた。」「表題作だけでは物足りない、と不満に思った途端、輪舞のように展開していく宇喜多の物語に昂奮した。最後があざとい、という意見もあったが、私はカタルシスに感じた。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』平成27年/2015年3月号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 深緑野分 | ◎ | 30 | 「私は本作品を推した。」「主人公の小さな世界から始まって、次第に戦争の中に突き進み、その恐ろしくグロテスクな面を浮き彫りにしていく構成もよい。」「第二次大戦のアメリカ兵に材を取っているが、どの時代のどんな人物を題材にしようが、文学は自由だ。問題は描かれるテーマにあって、この自由さを失っては小説は消滅する。」「敢えて苦言を呈すれば、ストーリー中のミステリー風味には、興を殺がれた。」 | |
| △ | 30 | 「達者な書き手であることは確かなのだが、つるりと喉越しのよいゼリーを食べた後のように、読後もまだ物欲しい気持ちが残る。」「気になったのは、どの短編もパターンが似通っていることだ。男二人に、女が一人現れて魔性ぶりを発揮する、というストーリーが多い。女の側の視点が欠落しているために、男たちの魅力が褪せる。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成28年/2016年3月号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ○ | 30 | 「浄瑠璃作者・近松半二の、浄瑠璃を中心に回る日々。軽妙な大阪弁で緩和されてはいるものの、その創作の様は息苦しいほどである。最後の「浄瑠璃腹がくちくなる」という台詞は、虚構にまみれることに倦んだ者の台詞として素晴らしかった。我々も、小説腹がくちくなる時がくるのだろうか。」 | ||
| 朝倉かすみ | ○ | 17 | 「独特のリズムを持つ、切れのいい文章と、的確な描写。」「ドラマ性をわざと排除した構成も、恋人同士それぞれの遠慮と覚悟を象徴していて秀逸だったと思う。受賞を逃したのは、返す返すも残念だ。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』令和1年/2019年9・10月合併号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 小川哲 | ○ | 20 | 「この作者特有の勘所が随所に見られる。特に出だしの一行の魅力は強烈だ。」「どの短編も、どこに着地するかわからないスリルがあり、知的かつ豪腕。とても楽しんだ。」「私は作者の背骨の強度に惹かれた。」 | |
| △ | 22 | 「文体は簡潔でリズムがあり、描写もうまい。個人的には、流刑になったピウスツキの生涯が劇的だっただけに、主人公ヤヨマネクフがうまく彼に絡まないのが残念だった。」 | ||
| 「どんな形の読書を強いられたとしても、作品の数だけ楽しむ方法はいくらでもあるのだが、どうしても受容できないものもある。それは、背骨が感じられない作品である。(引用者中略)作者がもっとも面白いと思う勘所が押さえられている作品、とでも言えばいいのだろうか。(引用者中略)それがないと、どんなにうまく書かれていても、心には残らない。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和2年/2020年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 坂上泉 | ○ | 31 | 「大阪市警視庁と国警という戦後の混乱を象徴するような刑事コンビが捜査に当たる、という設定もうまかった。場面転換、描写、登場人物の台詞も優れていて、新人とは思えなかった。その勢いと巧さを買って推した。ただ、気になったところもある。まず、この謎には新味がないこと。それから、実在の人物をモデルとした人物が多数登場して楽しい反面、物語が年表めいて狭くなるきらいがある。」 | |
| △ | 15 | 「圧倒的な安定感がある。」「「閨仏」のようなすっとぼけた話も書けるのだから、作者はなかなか強かである。連作短編集かと思ったら、ストーリー仕立てでオチがついていた。この作品は、多くの人に愛されることだろう。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』令和3年/2021年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 永井紗耶子 | ○ | 27 | 「主人公・周子と、北条政子の人物造型が鮮やかだった。」「女には女の政治があるという京の女の論理と、己の情そのままに振る舞う政子とソリが合うはずがない。」「かように女性作家が描く、鎌倉武士の女性の世界は滅法面白い。欲を言えば、周子の視点で物語が進んでゆくため、海野幸氏の人となりなど、もう少し知りたくもあった。」 | |
| △ | 14 | 「好感を持って読んだ。特に「星の随に」は、私好みだ。どれも上手く、文句のつけようがない。」「ただ、ギラリとしたものを求める人には、少しシンプルに過ぎるかもしれない。」 | ||
| 「小説世界に没頭できるのは、主人公もしくは登場人物の主体性に負うところが大きい。共感できれば、するするとその世界に入り込めるし、反感を持てば、その人物と小説世界の調和について考え続けることになる。反感以前に納得できない場合は辛い。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和4年/2022年9・10月合併号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 嶋津輝 | ○ | 19 | 「女が誰にも言えずに一人苦悩する姿を描いている点に深く共感する。」「市井の片隅に生きる女たちの世界を、女でしか書けない視点で描いた作者の勇気と筆力に感動した。」 | |
| △ | 27 | 「生まれて生きて死ぬ。ヒトも熊も自然界の一部でしかないというシンプルさ。」「作者は北海道の厳しい自然を活写し、「熊爪」という熊に近いヒトを巧妙に造型した。前人未踏の山に分け入るような仕事である。」 | ||
| △ | 21 | 「二作とも京都が舞台の、いい具合に肩から力が抜ける面白い読み物だ。」「表題作「八月の御所グラウンド」は、野球をテーマにした青春小説の趣がある。確かに、八月の暑いグラウンドでは、鮮やかな白昼夢が起きそうだ。だから、むしろリアルで、悲しく感じられた。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』令和6年/2024年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 岩井圭也 | ◎ | 25 | 「私が推したのは『われは熊楠』だ。文章は簡潔ながらも刃が突き刺さるような鋭さがあり、語彙が豊富で愉しい読書だった。」「一生を追うには紙数が足りないようだ。(引用者中略)だが、まるで人間Googleを目指しているかのような、知識の所有に奔走した熊楠の狂的な一面は充分に描かれている。」 | |
| □ | 13 | 「タイトルが、パンデミックのもじりであるとは、指摘されるまで気付かなかった。」「全体的に薄い味付けである分、この作者のさらりとしつつも、こくのある旨みがよく出ている。「特別縁故者」が秀逸だった。」 | ||
| 「短編集の場合、粒ぞろいでなければならない、と言ったのは他選考委員だが、その通りだと思う。」「各作品の相対的評価を試みるも、選考会は長引いて疲弊した。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和6年/2024年9・10月合併号 |
||||
| 選考委員 桐野夏生 |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 荻堂顕 | ○ | 18 | 「圧倒的筆力と抜群の文学的直感を感じた。」「対立の中で生きる者は、高慢と敗北を交互に噛み締める。女性の描き方、そして時代を表すディテールに、若干の違和を感じることもあったが、結末の苦みも含めて愉楽の読書だった。」 | |
| □ | 19 | 「科学という観点から暮らしを見つめると、こんなドラマが生まれるという、この作者にしかできない独創性が光る。素材を見つける視点と、簡潔でうまい文章が素晴らしい。」「気になった点があるとしたら、タイトルだろうか。短編集に纏める際に、ほとんどの短編を改題されているが、やや凝り過ぎに思える。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』令和7年/2025年3・4月合併号 |
||||