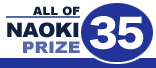
選評の概要
140.141. 142. 143. 144. 145.
146. 147. 148. 149. 150.
151. 152. 153. 154. 155.
156. 157. 158. 159. 160.
161. 162. 163. 164. 165.
166. 167. 168. 169. 170.
171. 172. 173. 174.
| 生没年月日【注】 | 昭和35年/1960年12月23日~ | |
| 在任期間 | 第140回~(通算17.5年・35回) | |
| 在任年齢 | 48歳0ヶ月~ | |
| 経歴 | 本名=矢部みゆき。東京都生まれ。東京都立墨田川高校卒。 | |
| 受賞歴・候補歴 |
|
|
| サブサイトリンク | ||
| 処女作 | 「我らが隣人の犯罪」(『オール讀物』昭和62年/1987年12月号) | |
| 直木賞候補歴 | 第105回候補 『龍は眠る』(平成3年/1991年2月・出版芸術社刊) 第106回候補 『返事はいらない』(平成3年/1991年10月・実業之日本社刊) 第108回候補 『火車』(平成4年/1992年7月・双葉社刊) 第115回候補 『人質カノン』(平成8年/1996年1月・文藝春秋刊) 第116回候補 『蒲生邸事件』(平成8年/1996年10月・毎日新聞社刊) 第120回受賞 『理由』(平成10年/1998年6月・朝日新聞社刊) |
|
| サイト内リンク | ▼小研究-記録(候補回数) ▼小研究-ミステリーと直木賞 ▼直木賞受賞作全作読破への道Part1 |
|
下記の選評の概要には、評価として◎か○をつけたもの(見方・注意点を参照)、または受賞作に対するもののみ抜粋しました。さらにくわしい情報は、各回の「この回の全概要」をクリックしてご覧ください。
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 池井戸潤 | ◎ | 28 | 「〈現実への解釈を変えるのではなく、現実そのものを、ベタな人間の愚直な奮闘で変えていくことだってできる〉という希望(引用者中略)に、強く心を動かされました。」「(引用者注:「花や散るらん」と共に)日々の暮らしを覆う漠然とした不安と閉塞感に、人がよろず自信を失いがちな今日だからこそ、こういう作品に直木賞を受賞してもらいたいと思いました。」 | |
| 葉室麟 | ◎ | 39 | 「史実を能動的に自在に操ることで生まれる〈作り話の妙味〉(引用者中略)に、強く心を動かされました。」「(引用者注:「鉄の骨」と共に)日々の暮らしを覆う漠然とした不安と閉塞感に、人がよろず自信を失いがちな今日だからこそ、こういう作品に直木賞を受賞してもらいたいと思いました。」 | |
| ○ | 36 | 「月並みな表現ながら〈いぶし銀の味〉なのですが、個々の作品にはピリッとした企みが隠されていることが嬉しいのです。」「表題作は、追う者と追われる者のあいだに発生する〈清算〉がテーマです。普通は清算を要求するのは追う者の側ですが、この作品では追われる者が追う者に決死の清算を迫り、それを仙道刑事が、ヒーロー然としてやり過ごせないところに新鮮なリアルを感じました。」「読んでいて、だから短編は面白いんだと思い、短編を書きたくなる作品集でした。」 | ||
| △ | 41 | 「白石さんには大変申し訳ないのですが、私はこの中編二作の作品集に対して何とも勘違いなアプローチをしてしまい、最後までそこから抜け出すことができませんでした。」「後半の「かけがえのない人へ」では、主人公の〈みはる〉が前半の〈なずな〉であるとこれまた勝手に思い込み(引用者中略)それが読み違いだとわかると、情けなくもまた迷子になってしまいました。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成22年/2010年3月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 姫野カオルコ | ◎ | 120 | 「(引用者注:「天地明察」とともに)丸をつけて、選考会に臨みました。」「私はキリスト教の「聖人伝」として読みました。倉島泉という黒い子羊が聖人になるまでの物語です。」「読後、自分のなかに溜まっていた自分ではどうすることもできない澱が、いくばくかでもこの作品によって浄化された気がして、静かに涙しました。姫野さん、支持しきれなくてごめんなさい。でも、この小説を書いてくれてありがとう。本を閉じたとき、多くの読者がそう呟くに違いない秀作です。」 | |
| 冲方丁 | ○ | 18 | 「(引用者注:「リアル・シンデレラ」とともに)丸をつけて、選考会に臨みました。」 | |
| △ | 16 | 「冒頭の手記を見た瞬間に、どんな仕掛けがほどこされているのだろうとワクワクしました。(引用者中略)この設定ならもっといろいろなことができるのに、もったいない――と考えてしまうのは、私がジャンル作家である所以で、評者としては困った性癖でしょう。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成22年/2010年9月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 貴志祐介 | ◎ | 54 | 「B級ホラーのノリでこの大長編を書ききった豪腕と、単独犯による大量殺人という扱いにくい素材を恐れなかった勇気に、私は票を投じました。」「読者のなかには、「でもハスミンってカッコいいよね」と感じる人もいるはずです。一方で、そういう読み筋に驚いて眉をひそめる読者もいる。それがこの作品の勝利です。」 | |
| □ | 29 | 「開化もので遊里ものという二段重ねの高いハードルに挑み、「あ、ここで飛び越えたな」という揺れを一切感じさせず、見事にクリアしている秀作です。実は私はこの二つの素材が苦手で、読み始めた時には不安だったのですが、すぐ引き込まれて夢中になりました。」 | ||
| □ | 20 | 「大人の視点を排し、慎一(引用者注:少年)にすべてを託して複雑な人間関係と母親の恋愛を描くのは、大胆な挑戦でした。そのチャレンジングな姿勢が今回の御受賞を引き寄せたのだと思います。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成23年/2011年3月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 原田マハ | ◎ | 27 | 「(良い意味で)大風呂敷を広げ、知的な興奮を与えてくれた『楽園のカンヴァス』を(引用者注:私は)推していた」「日常の繊細な、悪くいえばちまちました感情の呪縛から飛翔し、思い切って贅沢な設定と大胆な謎を作品の核に据え、一幕の知的冒険劇を観せてくれました。この作品が今、エンタテイメント読書界に登場してきたことの価値は、計り知れないほど大きい。」 | |
| △ | 31 | 「私は賛成票を投じていませんでした。」「でも(弁解がましいですが)、反対意見を押し戻すだけの強い賛意を集め、会心の受賞になったのではないでしょうか。私も、「芹葉大学の夢と殺人」は、同じような素材を扱った多くの小説を圧する傑作だと思います。〈夢を持って生きているはずの若者が、いつの間にか夢に人生を喰われている〉姿に、げんなりするようなリアリティと、もの悲しい説得力がありました。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成24年/2012年9月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 宮内悠介 | ◎ | 86 | 「DX9は、楽器として流通させるために〈歌う〉機能を持たされ、少女の外見をし、甘ったるい声で舌っ足らずにしゃべる量産型のロボットです。」「人間が神に問いかけるように、DX9が人間に、「かほどの試練を与えるならば、なぜ我らを創り賜うたか」と問いかけてきても、何の不思議もありません。」「その問いへの答えを、私は見出せませんでした。この作品は、答えを求めて読むものではない。「我々は何者で、どこへ行こうとしているのか」を考えるためにあるのです。直木賞にこういう受賞作があってもいい――むしろあるべきだと思いましたので、強く支持しました。」 | |
| △ | 14 | 「救済されるべき社会の構造的欠陥としての〈貧困〉ではなく、数値化することもできないけれど、かつては多くの日本人が実感し、けっして忌避してばかりはいなかった生活苦というもの。『ホテルローヤル』は、それを描いて余すところのない秀作でした。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成25年/2013年9月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ○ | 22 | 「実は私は裏社会ものが苦手なので、『破門』をきちんと評するために必要な読書経験が足りず、選考会では各委員の評を聞かせていただくばかりでした。でもその結果、私がこの小説を楽しく味わい、テンポのいい会話にころころ笑ったのは当然のことだったのだとわかって安堵しました。」 | ||
| 米澤穂信 | ○ | 19 | 「既に他の文学賞も受賞している作品ですが、意外に厳しい評が集まり、事実関係の記述のミスも指摘されて、私は大変驚きました。」「私はこのハイレベルな短編の連打に魅せられました。表題作の「満願」には、松本清張の傑作「一年半待て」を思い出しました。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』平成26年/2014年9月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 青山文平 | ◎ | 35 | 「今回、個人的には青山文平さんの『鬼はもとより』を推しました。藩札という難しい題材を扱いながらリーダビリティが高いのは、主人公の抄一郎のどこか悟ったようなすっとぼけた魅力と、彼が江戸の経営コンサルタントとして直面する〈貧との戦い〉の苛烈さが、ラストまで絶妙なバランスを保っていたからだと思います。」 | |
| 大島真寿美 | ○ | 18 | 「選考会の評価は辛かった。○は私一人でした。それぐらい好みの分かれる小説だということですが、私は大好きです。」「私はホリーさんのような女性作家とは(たぶん)対極にいますし、私みたいなタイプが〈白い部屋〉をつくって籠もるようになったら、それはもう作家としてアウトでしょうが、そんなヒヤリとする部分も含めて、記憶に残る作品です。」 | |
| △ | 8 | 「明るくてエネルギッシュで奇天烈でナイーブな西加奈子ワールドの(現時点の)集大成である『サラバ!』のご受賞は、直木賞にとっても嬉しいことです。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成27年/2015年3月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ○ | 14 | 「ハイレベルの短編集で、私はとりわけ巻頭の「ひともうらやむ」と表題作が好きです。題材を問わず、優れた小説には、必ずどこかしらに巧まざるユーモアがある。今回の選考で、あらためて実感しました。」 | ||
| 梶よう子 | ○ | 26 | 「○は私一人でしたから、受賞には届かずとも、もっと熱弁をふるえばよかった。」「私は浮世絵が苦手です。(引用者中略)でも、この作品は面白かった。入り乱れる絵師や役者たちの人名に苦労することもありませんでした。作者の水先案内が的確だったからです。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』平成28年/2016年3月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 宮内悠介 | ◎ | 38 | 「私は『あとは野となれ大和撫子』を推しました。」「読後感の重い候補作が揃っていたなかで、架空の砂漠の国で政治的冒険を繰り広げる聡明で元気な少女たちのお話は、まさにオアシスのようだったからです。」「中央アジアの政治情勢にはてんで無知で関心も薄かった私ですが、これからはワールドニュースで「アラル海周辺地域」などの言葉を聞いたら注目します。これは物語が日常という現実に働きかけ、何かをチェンジした証でしょう。」 | |
| △ | 23 | 「輪廻転生という仕掛けを使って、当事者の二人以外は誰も幸せにしない恋愛というものの暴力性と理不尽さを描いた小説だと私は思っています。」「そういう読み方をするのは私の性格が歪んでいるからだろうかと密かに怯えつつ選考会に臨みましたら、各委員から「小説としての完成度は素晴らしいが、物語としては薄気味悪い」というお声を聞いて安堵しました。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成29年/2017年9月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ○ | 14 | 「宮沢賢治がどこまでもお父さんを愛する息子だったことを、自分がそのように愛されていると気づかないほど深く息子を愛している当のお父さんの視点から、奇をてらわず抑制を効かせ、平易で明快な言葉で、そこに日向を置くように暖かく穏やかに綴った作品」「受賞はほぼ満場一致で決まりました。」 | ||
| 澤田瞳子 | ○ | 31 | 「私は(引用者注:「銀河鉄道の父」と友に)『火定』も推しました。」「私は『火定』がそうしているように、基本的には現代人の読者が理解しやすいように書いていいと思うのですが、タイトルの由来であり、この作品のテーマを象徴する〈火定入滅〉の思想は大乗仏教のもので、この時代にはまだふさわしくないのではないかという(引用者注:他の委員からの)指摘には「う~ん」と唸ってしまいました。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』平成30年/2018年3月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 上田早夕里 | ◎ | 45 | 「推しました。」「堅実で抑制的で、パンデミック・パニックSFや、反戦・反化学兵器をテーマにしたフィクションにありがちな感情的な描写やストーリー展開はありません。登場人物の陰影も淡く、ちょっと落ち着きすぎているのでは? と思うほどに、じっくりゆっくりと物語が展開されていきます。(引用者中略)この禁欲的なスタンスが私には新鮮でしたし、学ぶべきところがたくさんあると思いました。」 | |
| △ | 15 | 「残念ながら私の感覚はこの『ファーストラヴ』という作品世界に合わなかったらしく、支持できなかったのですが、体温に近いような酷暑のなかで、この物語に浸っているときに覚えた冷ややかな恐怖と閉塞感、作中で暴かれてゆく秘事への嫌悪感には忘れがたいものがありました。」 | ||
|
選評出典:『オール讀物』平成30年/2018年9月号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ◎ | 18 | 「ほぼ満票の圧勝も当然の力作でした。」「沖縄だけでなく、全ての苦闘している人びと、圧迫されている人びと、辛い現実をかき分けながら希望を目指して前進している人びとに、「そろそろほんとうに生きるときがきた」とエールを贈る物語。」 | ||
| 垣根涼介 | ○ | 31 | 「(引用者注:「宝島」と共に)もう一作、垣根涼介さんの『信長の原理』も推したのは、この作品が戦国ものの歴史小説としてユニークな詠み心地を与えてくれたからです。ポップで軽やかで、ポピュラーサイエンスの本やビジネス書的な面白さ。」「ただ選考会で、信長に関する基本的な歴史考証にいくつか定説と異なる記述があり、これが意図的なものだとするとその意図が物語に回収されていないし、うっかりミスだとすれば手痛い失点だ――というご意見を聞き、そこで諦めました。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』平成31年/2019年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ◎ | 16 | 「風格さえ漂う歴史小説ですが、冒険小説としても面白いので、受賞を機会に多くの若い読者のもとに届いてほしいと思います。」 | ||
| 誉田哲也 | ◎ | 27 | 「現代社会を舞台にした大人のザッツ・エンタテイメントなこの作品は、直木賞の幅と懐の深さをアピールしてくれるとも思いました。」「今このタイミングで顕彰されるべき作品でした。」「「社会の治安と個人の自由にどこまで互換性を持たせるか」。そう遠くない将来、この問題が私たちの日常に直に触れる形で選択を迫ってきたとき、多くの読者がこの作品を思い出し、膝を打つことになると私は信じています。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』令和2年/2020年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ◎ | 37 | 「私は安心して推すことができましたが、この物静かな連作短編集の凄さは、六編の短編一つ一つの「凄い点」に違いがあることです。」「「閨仏」はもうアイデア勝負の一発ネタ。同時に、この話を下品に落とさず、何とも微笑ましいエピソードに丸めてしまう素直な文章力。これは技術だけでなく、作者の人柄の力でもあるでしょう。」「(引用者注:「オルタネート」と共に)票を投じました。」 | ||
| 加藤シゲアキ | ○ | 23 | 「今時こんな健康的な高校生青春ドラマが読めるとは! と感激しました。」「(引用者注:マッチングアプリ「オルタネート」について)年齢制限ではなく、高校生でなければ使えない(使わせない)という線引きは、何気ないようでいて残酷ですし、作者の現実を見る目の鋭さを覗わせるものです。」「(引用者注:「心淋し川」と共に)票を投じました。」 | |
| 「今回は、選考を終えて痛感したことを、そのまま選評のタイトルにしました。」「今回、私は、できることなら二作受賞にしたいと願っていました。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和3年/2021年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| ◎ | 28 | 「新型コロナウイルスの世界的なパンデミックを、物語のなかでどのように描くか。様々なアプローチがあると思いますが、窪美澄さんの『夜に星を放つ』は、そのなかで最も自然体の優しいスタイルを選んで書かれた小説だと思います。ここで肝心なのは、「優しい」と「ぬるい」は決定的に違うということ。困難なことも辛いことも嫌なことも細かくちくちくと待ち受けている現実から目をそらさず、でも一人一人が個々の状況下で望める限りの幸せを得てほしい――。そんな作者の願いが伝わってくる読み心地でした。」 | ||
| 永井紗耶子 | ◎ | 69 | 「(引用者注:「夜に星を放つ」と共に)○をつけまして、決選投票でも支持したのですが、今一歩及ばず次点になってしまいました。」「勃興から衰退滅亡まで山のように書く材料がある鎌倉幕府と北条氏の歴史のなかで、大姫入内という(頼朝の鎌倉政権にとっては手痛いターニングポイントではありますが)地味な出来事をテーマに、終始声を張り上げず、演説もせず、穏やかに淡々と、主な登場人物みんなの心模様を丁寧にすくい取り、ひとつづりの長編小説に仕立て上げたこの腕前! ほれぼれしました。」 | |
|
選評出典:『オール讀物』令和4年/2022年9・10月合併号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 宮内悠介 | ◎ | 28 | 「一番に推しました。」「私は毎度、宮内作品を評する自分の語彙の乏しさに地団駄を踏みたくなります。」「見るからに労作、というページ数を費やさずに、軽やかに優しく読む者の世界を広げ得る、宮内さんの筆力にはいつも感嘆するばかりです。」 | |
| △ | 17 | 「(引用者注:「八月の御所グラウンド」と共に)形も色合いも食感も味わいもまったく異なる二種類のお菓子のようでした。(引用者中略)遠くかけ離れた二作でありながら、点数に大きな差はありませんでしたし、選考委員がみんなで熱っぽく、楽しく議論した二作でしたから、同時受賞は正しい結果だったと思います。」 | ||
| △ | 20 | 「(引用者注:「ともぐい」と共に)形も色合いも食感も味わいもまったく異なる二種類のお菓子のようでした。(引用者中略)遠くかけ離れた二作でありながら、点数に大きな差はありませんでしたし、選考委員がみんなで熱っぽく、楽しく議論した二作でしたから、同時受賞は正しい結果だったと思います。」 | ||
| 「今回はこの六作を候補作としてお預かりした時点で、「大変な選考になるなあ」と覚悟していました。予想通り久々の三時間越えの議論となり、帰宅したらふらふらでした。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和6年/2024年3・4月合併号 |
||||
| 選考委員 宮部みゆき |
||||
| 候補 | 評価 | 行数 | 評言 | |
| 逢坂冬馬 | ◎ | 42 | 「(引用者注:「逃亡者は北へ向かう」と共に)一位に推していまして、」「ひさびさに「作者の手のひらで転がされながら、どっぷりと物語にひたって翻弄される」楽しみを与えてくれる作品でした。」「いろいろ議論しているうちに、確かに細部に疑問点があったり、時制のずらし方がわかりにくかったり(これをパッと明快にしてしまうと物語の妙味も薄れてしまうのですが)、なかなか不利な展開になってしまって、小説を評じることの難しさに、今さらながら胃がきりきりしました。」 | |
| 柚月裕子 | ◎ | 41 | 「(引用者注:「ブレイクショットの軌跡」と共に)一位に推していまして、」「終盤、逃亡者の青年が「自分の人生に起きた出来事は、不運のせいではなく、全て自分の選択の結果だったのだ」という痛ましい洞察にたどり着くシーンでは、涙してしまいました。しかし、それでも――という物語の決着の付け方に、柚月さんの作家としての矜持があると思いました。」「私にとってはこの作品が受賞作です。」 | |
| 「今回は受賞作を選ぶことができませんでした。四時間あまり議論しまして、最終的には二作で決選投票をしましたが、得点が過半に達する作品がなかったということです。」 | ||||
|
選評出典:『オール讀物』令和7年/2025年9・10月合併号 |
||||

